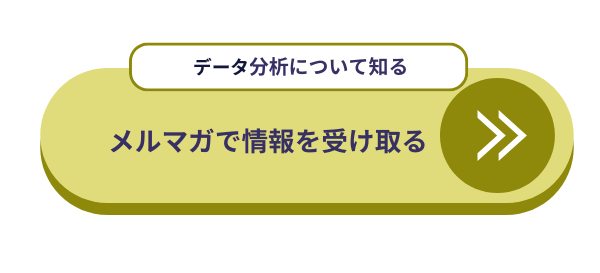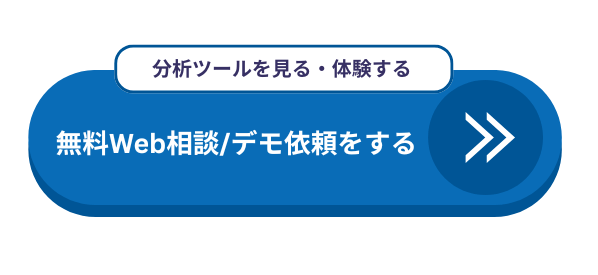エリアマーケティングラボ
10月18日は「統計の日」!統計とは?ビジネスでの活用も。
2025年10月1日号(Vol.182)
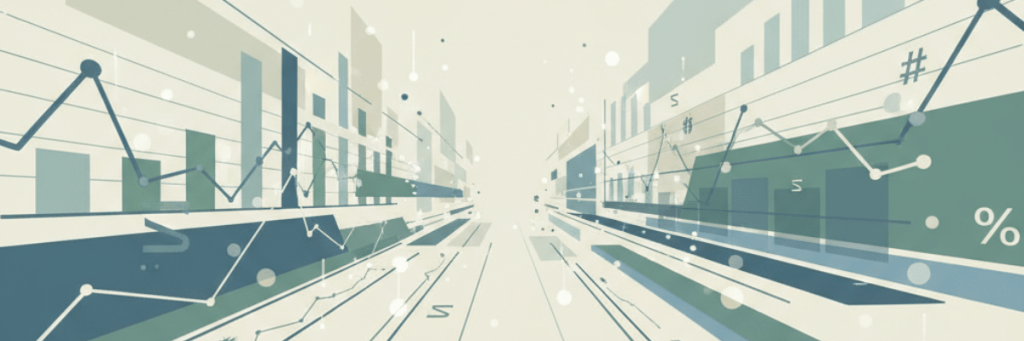
はじめに
10月18日が「統計の日」であることをご存知でしょうか。私たちの社会や経済、そして日々の暮らしを映し出す「数字」に光を当てる、年に一度の特別な日です。そして、今年2025年(令和7年)10月には、5年に一度の国家的な一大プロジェクトである「国勢調査」が実施されます。これは、統計が単なる過去の記録ではなく、未来を形作るための重要な情報基盤であることを改めて認識する絶好の機会と言えるでしょう。
しかし、「統計」と聞くと、どこか難しく、自分たちのビジネスとは縁遠いものだと感じてしまう方も少なくないかもしれません。
本コラムでは、そのイメージを覆すべく、「なぜ統計の日が制定されたのか?」という素朴な疑問から、統計が国家の運営や企業のマーケティング戦略、さらには最先端のAI技術に至るまで、いかに深くダイナミックに関わっているのかを解説します。
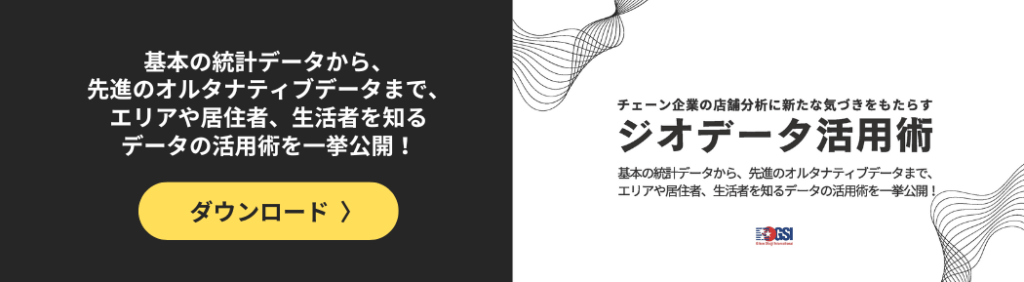
10月18日「統計の日」とは?その由来と目的
近代統計の始まり:「府県物産表」公布の日
「統計の日」が10月18日と定められたのには、日本の近代化における重要な歴史的背景があります。その起源は、明治維新から間もない1870年(明治3年)10月18日(旧暦9月24日)に遡ります。この日、明治政府は太政官布告をもって、現在の生産統計の礎となる「府県物産表」に関する規定を公布しました。
これは、日本が初めて全国規模で統一された基準に基づき、各地域の生産物を体系的に調査・把握しようとした画期的な試みでした。封建的な社会から近代国家へと生まれ変わろうとする中で、自国の国力を客観的な「数字」で把握することは、富国強兵を目指す政府にとって不可欠な第一歩だったのです。この「府県物産表」の公布こそが、日本の近代統計史の幕開けを象徴する出来事であり、10月18日はその記念すべき日として選ばれました。

国民と統計をつなぐための制定
この歴史的な日付が正式に「統計の日」として制定されたのは、それから約100年後の1973年(昭和48年)7月3日の閣議了解によるものでした。その目的は、国民一人ひとりに対して統計の重要性への関心と理解を深め、国勢調査をはじめとする各種統計調査へのより一層の協力を得ることにあります。政府が正確な統計を作成するためには、国民からの真実に基づいた回答が不可欠です。統計の日は、その協力関係を築き、社会全体でデータリテラシーを高めていくための国民的なキャンペーンの日として位置づけられています。
国際的な統計の重要性:「世界統計の日」(10月20日)
統計の重要性は、日本国内だけの話ではありません。国連は2010年、10月20日を「世界統計の日(World Statistics Day)」と定め、以降5年ごとに世界中でその意義を祝っています。この国際デーは、信頼性の高い公的統計が、持続可能な開発目標(SDGs)の達成や、各国の的確な政策決定、そして国民の意思決定においていかに重要な役割を果たしているかを世界規模で認識するために設けられました。
日本の「統計の日」が、明治時代の国家形成という内向きのベクトルから生まれたのに対し、国連の「世界統計の日」は、グローバル化が進む現代において、気候変動や経済危機といった国境を越える課題に立ち向かうための国際協調という外向きのベクトルから生まれています。
この二つの記念日の存在は、統計の役割が、一国の自己理解のためのツールから、地球規模の課題を解決するための世界共通言語へと進化してきたことを象徴していると言えるでしょう。なお、インドが統計学者の誕生日にちなんで6月29日を統計の日とするなど、世界各国が独自の日を定めており、統計への価値観が普遍的であることがうかがえます。

令和の「統計の日」:標語とイベントに注目
時代を映す鏡:統計の日の標語コンテスト
総務省は毎年、次年度の「統計の日」のポスターなどに活用する標語を広く一般から募集しています。小学生から一般、統計調査員、公務員まで幅広い部門で募集されるこのコンテストの入選作品は、その時々の社会が統計に何を期待しているかを映し出す、興味深い指標となります。
• 令和6年度(2024年)特選作品:『今を知り 未来つくろう 統計パワー』
この作品は、統計が現状把握(今を知り)にとどまらず、未来を創造するための能動的な力(未来つくろう)を持つという、ポジティブで力強いメッセージを伝えています。
• 令和7年度(2025年)特選作品:『統計で今を「サーチ」、未来を「察知」』
「サーチ(探索)」と「察知(感知)」という言葉遊びを用い、統計の持つ現状分析と未来予測の二つの側面を見事に表現しています 。データドリブンな意思決定が求められる現代社会の本質を捉えた秀逸な標語と言えるでしょう。

これらの標語は、統計がもはや専門家だけのものではなく、誰もが未来をより良くするために活用できる「パワー」であり「ツール」であるという認識が社会に広まっていることを示しています。特に、令和6年度の一般の部佳作作品である『AIも 正しいデータ あればこそ』という標語は、現代のビジネス環境を的確に言い表しています。これは、どれだけ高度なAI技術を導入しても、その基盤となるデータの品質が低ければ意味がないという、「ガベージイン・ガベージアウト(ゴミを入れればゴミしか出てこない)」の原則を平易な言葉で表現したものです。この視点は、まさに正確で信頼性の高いデータと、それを活用するための高度な分析ツールを提供する企業の価値そのものを裏付けています。
統計を身近に:全国で開催される主なイベント
「統計の日」を中心とする期間には、統計をより身近に感じてもらうためのイベントが全国各地で開催されます。
・統計データ・グラフフェア:
新宿駅西口広場などで開催され、全国の小中学生や高校生が作成した優れた統計グラフが展示されます。
・全国統計大会:
国や地方公共団体の統計関係者が一堂に会し、統計功労者の表彰や研究発表が行われる、国内最大級の統計関連イベントです。
これらのイベントは、統計が私たちの社会を支えるインフラであることを再認識させ、データに基づいた社会のあり方を考えるきっかけを提供してくれます。
日本の統計制度:歴史と法的根拠
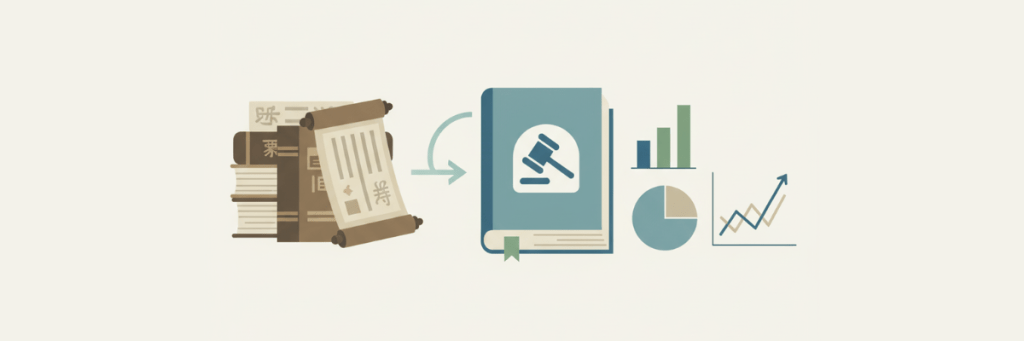
近代統計の礎:杉亨二による制度設計
日本における統計の起源は、律令制下の「戸籍」や、豊臣秀吉の「太閤検地」などに遡りますが 、調査方法が統一されておらず、正確性にも課題がありました。
日本の近代統計制度が本格的に始まったのは明治時代です。1871年(明治4年)に太政官正院に「政表課」が設置され、国の公式業務となりました。この礎を築いたのが、初代統計局長と称される杉亨二(すぎ こうじ)です。彼は、欧米の知識を取り入れ、統計の標準化や専門家の育成に尽力し、現在の高度な統計システムの基礎を設計しました。
公的統計の再定義:2007年「統計法」の全面改正
現代日本の統計制度を支える根幹は「統計法」です。戦後の1947年に初めて制定されましたが 、2007年(平成19年)に全面的に改正され、統計制度は大きなパラダイムシフトを遂げました。
新しい統計法の目的は、「公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることにかんがみ …公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与すること 」と定められています。
この改正の核心は、公的統計を「政府のためのもの」から、「社会全体のための情報基盤(インフラ)」へと再定義した点にあります。これにより、これまで厳しく制限されていた統計データの二次利用に関する規定が整備され 、学術研究や民間企業が、匿名化された調査票情報などを活用する道が大きく開かれました。
2007年の統計法改正は、国が収集したデータを公共財として開放し 、民間企業がそのデータに付加価値を与えることで新たなイノベーションを生み出す「データエコノミー」の法的土台を築いた画期的な出来事と言えます。
日本の代表的な統計調査:社会の二つの地図
新しい統計法の下で、社会の「情報基盤」として整備されている公的統計。その中でも、社会全体の姿を最も根源的に捉えるために行われるのが「基幹統計」です。ここでは、その代表格である二つの大規模調査、「国勢調査」と「経済センサス」について解説します。これらは、いわば日本社会の「人」と「ビジネス」を映し出す、最も基本的な地図と言えるでしょう。
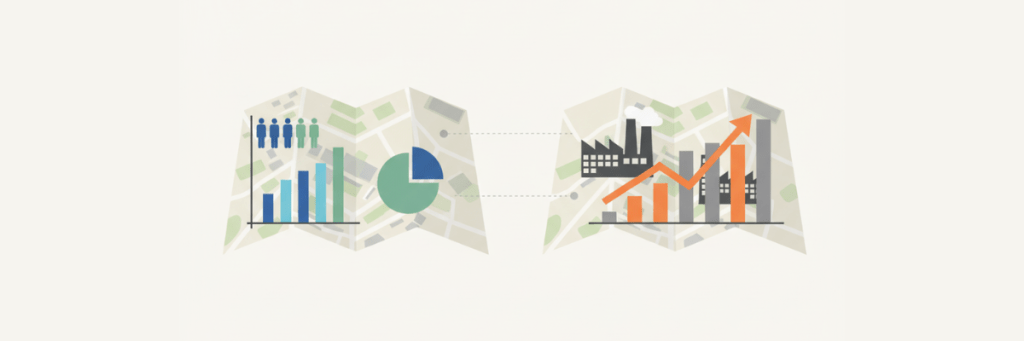
人の地図:5年ごとの国家プロジェクト「国勢調査」
国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯を対象として、5年ごとに実施される、国の最も重要かつ基本的な統計調査です。1920年(大正9年)に第1回調査が実施されて以来、戦争直後の1945年を除いて継続されており、2025年(令和7年)の調査で22回目を迎えます。
調査項目は、男女の別、出生の年月、配偶者の有無、就業状態といった個人に関する基本的な事項から、世帯員の数、住居の種類といった世帯に関する事項まで多岐にわたります。
この調査結果から得られる人口は「法定人口」として、衆議院議員の選挙区割りや、地方交付税の算定基準など、国の根幹をなす制度の基礎となります。また、少子高齢化対策、防災計画の策定、社会福祉施策の立案など、私たちの暮らしに直結するあらゆる行政サービスの計画に不可欠なデータを提供します。
★当社でもエリアマーケティングに活用できる町丁目やメッシュという小地域単位の国勢調査データを提供しています。
https://www.giken.co.jp/datalineup/statistics/censusdata/

ビジネスの地図:「経済の国勢調査」経済センサス
経済センサスは、一部の農林漁家などを除く、国内のすべての事業所および企業を対象とする大規模調査で、「経済の国勢調査」とも呼ばれています。かつては産業分野ごとに別々に行われていた調査を統合し、日本の産業構造全体を包括的に把握することを目的に、2009年から始まりました。
経済センサスは、目的の異なる二つの調査から構成されています。
• 経済センサス-基礎調査:
全国の事業所・企業の名称、所在地、従業者数といった基本的な構造を把握し、あらゆる統計調査の土台となる「事業所・企業のマスターデータ(母集団情報)」を整備することを目的とします。
• 経済センサス-活動調査:
基礎調査で整備された名簿を基に、売上高や費用、設備投資額など、企業のより詳細な経済活動の実態を把握することを目的とします。
これらの調査結果は、GDP(国内総生産)統計の精度向上や、国・地方公共団体の産業振興策、中小企業支援策の立案などに活用されます。そして民間企業にとっては、市場規模の把握、特定エリアの産業集積の分析、BtoBマーケティングのターゲットリスト作成など、経営戦略を立てる上で極めて価値の高い情報源となります。
★小地域単位の経済センサスデータ
https://www.giken.co.jp/datalineup/statistics/economic_census/

統計情報の活用:政策から最先端の企業マーケティングまで
国勢調査や経済センサスといった大規模調査によって収集された統計データは、どのようにして社会を動かす力に変わるのでしょうか。その活用範囲は、公正な社会基盤を築くための公的政策から、競争を勝ち抜くための企業戦略まで、驚くほど広範にわたります。
※本パートでの企業や自治体の事例はインターネット等の公開情報から当社調べで作成したものです。
公的政策:EBPM(証拠に基づく政策立案)の推
現代の行政運営において、EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)は世界の潮流です。勘や経験ではなく、客観的なデータ(証拠)に基づいて政策を企画・立案し、その効果を測定・評価するアプローチです。公的統計は、このEBPMの根幹をなす最も重要な「証拠」です。
• 防災・減災計画:
国勢調査の年齢別人口や世帯構成データを地図上に重ね合わせることで、災害時に特に支援が必要な高齢者世帯が集中するエリアなどを特定し、避難所の適正配置やきめ細やかな避難計画の策定が可能になります。
• 都市計画・インフラ整備:
昼間人口と夜間人口のデータを分析し、人の流れを把握することで、道路や鉄道、バス路線の最適化や、公共施設の需要予測に役立てています。
• 社会福祉:
神奈川県葉山町では、ごみ収集拠点の不適切な利用状況をデータでモニタリングし、具体的な課題を特定。科学的な手法(RCT)で対策の効果を検証するなど、地域社会の身近な課題解決に直結する活用例もあります。

企業経営:市場を読み解き、競争を勝ち抜く戦略
民間企業にとって統計データは、ビジネスという大海原を航海するための羅針盤です。市場トレンドの把握、顧客理解、競合との差別化を図る上で、データに基づいた意思決定は不可欠です。
• 需要予測と業務効率化:
回転寿司チェーンの「スシロー」は、寿司皿のICタグから膨大なデータを収集・分析し、レーンに流す寿司の種類と量をリアルタイムで最適化。顧客満足度を高めながら、食品廃棄量を従来の4分の1にまで削減することに成功しました。
• パーソナライゼーション:
ECサイトの「Amazon」は、全ユーザーの膨大な行動データを解析し、高い精度のレコメンデーション機能を実現。データが顧客一人ひとりに最適化された買い物体験を生み出しています。
公的統計データという土壌の上で、民間企業が独自のデータを組み合わせ、新たなサービスやビジネスモデルを創造する「データエコノミー」の好循環が生まれています。公的データをビジネスで活用可能なインテリジェンスへと転換する役割を担う企業は、この価値創造プロセスにおいて重要な結節点となっています。

エリアマーケティング:統計データをビジネスの「武器」に変える
ここからは、より具体的で実践的なビジネスの現場に焦点を当てます。特に、店舗ビジネスや地域密着型のサービスにおいて、統計データはどのようにして競争優位性を生み出す「武器」となるのでしょうか。その答えが、「エリアマーケティング」という考え方にあります。
すべてのビジネスは「ローカル」である
エリアマーケティングとは、「市場は地域ごとに異なる特性を持つ」という基本認識に基づき、マーケティング戦略を地域単位で最適化していくアプローチです。全国一律の画一的な戦略ではなく、それぞれのエリアの人口構成、ライフスタイル、所得水準、競合状況といった特性を深く理解し、その地域に最も響く方法で商品やサービスを提供することを目指します。
ミクロな現実を捉える:商圏調査(商圏分析)の重要性
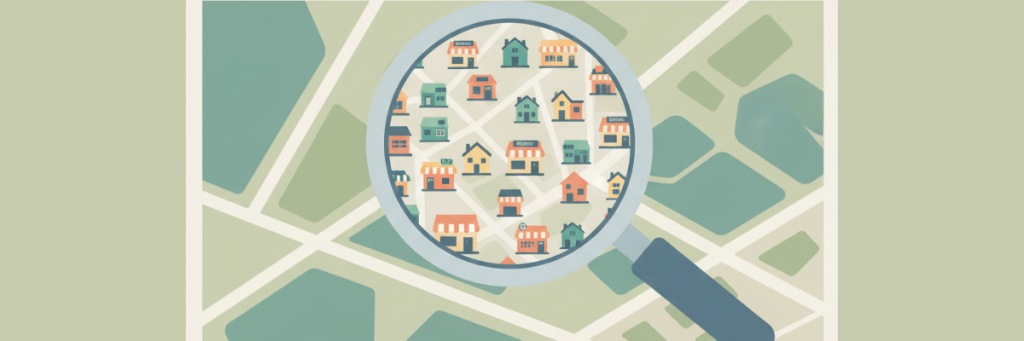
エリアマーケティングを実践する上で中核となるのが「商圏調査(商圏分析)」です。商圏とは、自社の店舗やサービスが顧客を引きつける地理的な範囲を指します。
商圏調査では、国勢調査や経済センサスなどの公的統計データに加え、自社の顧客購買データ、スマートフォンの位置情報(人流)データなど、様々な情報が統合的に用いられます。
商圏調査がもたらす重要な経営判断は以下の通りです。
• 新規出店戦略:
出店候補地の商圏を分析し、人口構成、所得水準、競合店の位置などを考慮することで、出店後の売上を高い精度で予測できます。これにより、感覚的な判断に頼った失敗を避けることが可能です。
• 販売促進の最適化:
ターゲット顧客層がどのエリアに多く居住しているかを特定し、そのエリアに絞ってチラシ配布やWeb広告を配信することで、無駄な広告費を削減し、費用対効果(ROI)を劇的に向上させます。
• 商品構成(MD)の最適化:
商圏の人々のライフスタイルや所得水準を理解することで、高級住宅街のスーパーではオーガニック食材を、学生街のコンビニではボリュームのある弁当を手厚くするなど、地域特性に合わせたMD戦略が可能になります。
エリアマーケティングは、マクロなトレンド(例:人口減少)だけでなく、ある地域では若年人口が急増し、別の地域では高齢化が極端に進行しているといったミクロな現実を正確に捉えることが可能です。このミクロな現実に即した戦略こそが、エリアマーケティングが「武器」と呼ばれる所以です。

商圏調査・エリアマーケティングに必須のツール:GIS(地図情報システム)
エリアマーケティングの強力なコンセプトを、現実のビジネスで実行可能なツールへと昇華させる技術、それが「GIS(Geographic Information System:地理情報システム)」です。GISは、統計データをビジネスの「武器」に変えるための、いわば究極のプラットフォームと言えるでしょう。

データの視覚化と統合:GIS(地理情報システム)の役割
エリアマーケティングを実行可能なツールへと昇華させる技術がGIS(Geographic Information System:地理情報システム)です。
GISは、「数字の羅列である統計データを、地図という直感的なインターフェース上に可視化するシステム」です。GISの本質は、様々な情報を「場所」という共通の軸で統合し、空間的な関係性を分析する能力にあります。
単なる地図作成ツールではなく、「何が起きているか」だけでなく、「それはどこで起きているのか」、そして「なぜそこで起きているのか」という問いに答えるための強力な分析エンジンなのです。
インサイトの発見:空間的なパターンと因果関係の可視化
GISを活用することで、見過ごされてきたビジネスチャンスや課題が地図の上に浮かび上がります。
• 自社の顧客データと国勢調査の年齢構成データを重ね合わせることで、「優良顧客が、実は特定の年齢層が多く住むごく限られたエリアに集中していた」という事実が判明するかもしれません。
• 競合店の位置データと自店の商圏を比較すれば、「A店とB店の商圏が大きく重複しており、激しい顧客の奪い合い(カニバリゼーション)が起きている」という問題点が可視化されます。
このように、GISは抽象的なデータを具体的な地理的文脈の中に置くことで、人間の脳がパターンや因果関係を認識するのを助け、新たなインサイトの発見を促します。

当社のエリアマーケティングGIS:MarketAnalyzer® 5
技研商事インターナショナルが提供するMarketAnalyzer® 5は、エリアマーケティングの高度な要求に応える、国内トップクラスのGISです。2,000社以上の導入実績があり、多くの企業の戦略的意思決定を支えています。
MarketAnalyzer® 5は、単なる地図ソフトではなく、エリアマーケティングに必要な機能を網羅した統合分析プラットフォームです。
・豊富な搭載データ:
国勢調査や経済センサスはもちろん、年収推計データ、消費支出データ、昼間人口データなど、多種多様な統計データが標準搭載されており、すぐに高度な分析を始めることができます。
・ 高度な分析機能:
重力モデルやハフモデルといった専門的な商圏分析手法を用い、新規出店の売上予測や既存店のポテンシャル評価を高い精度で行えます。
・ 競合分析:
地図上に競合店の情報をプロットし、自社との商圏の重なりや力関係を分析することで、戦略的な販売促進計画を立案できます。
GISは、異なる種類のデータを「地図」という一枚のキャンバスに統合し、混沌とした情報の中から意味のあるパターンと戦略的な示唆を浮かび上がらせる「意味生成マシン(Sense-Making Machine)」として機能します。
GIS「MarketAnalyzer® 5」無償提供実施中
AIによるデータ解釈の自動化:商圏レポートAIの衝撃
データ活用のボトルネック:分析結果の「解釈」
GISにより高度な分析が可能になりましたが、ビジネスの現場には、分析結果の「解釈」という最後の高いハードルが残されています。
地図やグラフを前にして、「で、結局このエリアはどういう特徴があって、私たちは次に何をすべきなのか?」という問いに、誰もが即座に答えられるわけではありません 。分析結果を分かりやすい言葉に翻訳し、意思決定者向けの報告書にまとめる作業には、専門的な知識と多くの時間が必要でした。この「データから意思決定まで」の最後の溝が、データ活用の最大のボトルネックとなっていたのです。
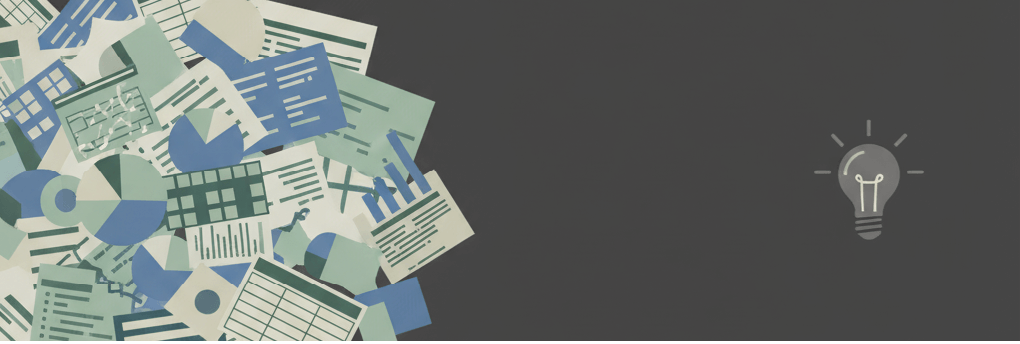
ラストワンマイルを埋める:MarketAnalyzer® 5「商圏レポートAI」
この「ラストワンマイル」問題を解決するために、技研商事インターナショナルが開発したのが、MarketAnalyzer® 5の機能である「商圏レポートAI」です。
この機能は、生成AI技術を活用し、指定した商圏内の膨大な統計データを自動で解析。そのエリアの特性を、人間が読むための自然な文章(ナラティブ)で要約し、Excel形式のレポートとして出力します。
AIは、人口動態、世帯構成、年収、消費傾向、商業特性といった多角的なデータを基に、そのエリアが持つ「物語」を自動で紡ぎ出します。例えば、「このエリアは、近年30代の子育て世帯の流入が著しく、教育関連への消費支出意欲が高いと推察される」といった、具体的な示唆に富んだレポートが、わずかな時間で生成されます。
★商圏レポートAIサービスページ
https://www.giken.co.jp/products/ai-generates-reports/

AIがもたらす「スピード」と「専門知の民主化」
商圏レポートAIがもたらす価値は、単なる業務効率化にとどまりません。
• 意思決定の高速化:
数日かかっていたレポート作成作業が、数分で完了します。これにより、マーケティングチームは戦略立案という、より創造的な業務に集中できるようになります。
• 専門知の民主化:
データ分析の専門知識がない営業担当者や店舗開発担当者でも、ボタン一つで専門家レベルのエリア分析レポートを入手できます。組織全体のデータリテラシーと戦略実行力が飛躍的に向上します。
• 文脈に応じたレポート生成:
レポート作成の際に、「誰が」「誰に」「何のために」といった条件を設定することで、AIが文脈を理解し、レポートの論調や強調するポイントを最適化します。
商圏レポートAIは、データの言語とビジネスの言語を翻訳する画期的な通訳者です。これまで熟練した人間のアナリストが担ってきた、データの統合、解釈、物語化という高度な認知プロセスを自動化する。これこそが、商圏レポートAIがビジネスにもたらす「衝撃」なのです。
まとめ:統計を活用し、データドリブンなビジネスの未来へ
10月18日の「統計の日」。その起源である明治時代の「府県物産表」から始まった日本の統計は、社会を正確に映し出す鏡として、また、未来を計画するための羅針盤として、絶えず進化を続けてきました。
本コラムでは、その歴史的な意義から、国勢調査や経済センサスといった現代社会の基盤をなす大規模調査、そしてそれらのデータが政策立案から企業の最先端マーケティングに至るまで、いかに力強く活用されているかを見てきました。
21世紀のビジネス環境において、データを理解し、活用する能力は、もはや一部の専門部署のスキルではなく、すべてのビジネスパーソンにとって不可欠なリテラシーとなっています。統計は、もはや無味乾燥な数字の集まりではありません。それは、市場の声であり、顧客のインサイトであり、未来のトレンドを示す、生きた情報です。
エリアマーケティングという戦略的な視点と、GISという強力なツール、そしてAIによる解釈の自動化。これらの組み合わせは、企業がデータという「宝の山」から真の価値を引き出すための、かつてない強力な武器となります。
もし、あなたが「統計の日」をきっかけに、自社のビジネスをデータという確かな根拠の上で成長させる次の一歩を踏み出したいとお考えなら、ぜひ私たちにご相談ください。技研商事インターナショナルのMarketAnalyzer® 5と商圏レポートAIは、データの中に眠る無限の可能性を解き放ち、あなたのビジネスを新たな成功のステージへと導くための、最も確かなパートナーとなるでしょう。
監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |
|
| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |
 |
電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)
Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/