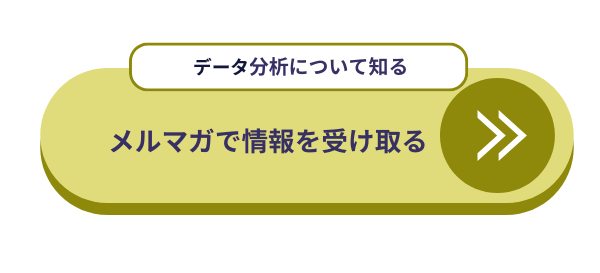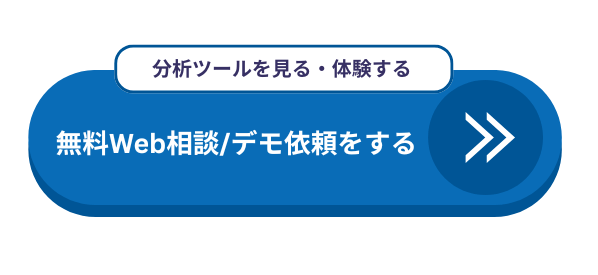エリアマーケティングラボ
地価マップで地域の土地価格を検索
2025年8月1日号(Vol.165)

はじめに:「地価マップ検索」の先にある、”真のエリア分析”とは
「地価マップ」というキーワードで検索してこのページにたどり着いた方は、おそらく特定の地域の土地価格に関心をお持ちなのではないでしょうか。背景には、新規出店の検討、不動産投資の判断、あるいは既存店舗の立地戦略の見直しといった、重要な意思決定が控えているのかもしれません。特に2025年7月1日には、国税庁から最新の路線価が発表され、地価に対する注目が一段と高まっています。
地価マップを見ると、東京・銀座の1平方メートルあたり4,808万円のような高額から地方の比較的手頃な価格まで様々です。しかし、地価が高い場所が必ずしも利益を生むとは限らず、地価が安い場所にチャンスがある可能性もあります。
地価は意思決定の一要素に過ぎず、正確な判断には地価マップの情報だけでなく、より深く多角的なエリア分析が必要です。このコラムでは、「一物五価」の考え方、2025年最新路線価に基づく地価動向と経済的背景、そして地価データに依存しすぎた戦略のリスクについて解説します。最終的に、地価マップを超えたデータドリブンなエリア分析手法を紹介し、土地の真の価値を見極める視点と判断材料を提供します。

「一物五価」を理解する:土地の価格はなぜ5つも存在するのか?
日本の不動産には「一物五価」という言葉があり、一つの土地に5つの異なる価格が存在します。これらは目的と算出基準が異なり、地価情報を正しく活用するためにはこの違いを理解することが重要です。例えば、相続税計算と店舗出店地の市場価値把握では参照すべき指標が異なります。ここでは、5つの主要な土地価格指標について解説します。
① 実勢価格(じっせいかかく)
実勢価格は「時価」とも呼ばれ、実際の売買で成立した価格です。市場の需給バランスや再開発計画、景気、売主・買主の事情など個別要因に影響されます。公的な一覧データはなく、国交省の「不動産取引価格情報検索」などで過去の取引事例を確認できますが、あくまで参考値です。
② 公示地価(こうじちか)
公示地価は国土交通省が毎年1月1日時点の「正常な価格」を3月に公表する、日本の土地価格の基本指標です。土地取引の客観的指標や公共用地取得価格、不動産鑑定の基準として活用されます。2名以上の不動産鑑定士の評価に基づき、土地鑑定委員会が価格を決定します。
③ 基準地価(きじゅんちか)
基準地価は都道府県が公表する価格で、公示地価を補完する役割を担っています。調査時点は7月1日で、都市計画区域外の土地も対象になります。
半年ごとの地価動向を確認できるため、「地価の速報値」としても活用されます。価格は不動産鑑定士1名以上の評価に基づいて決まります。
④ 相続税路線価(そうぞくぜいろせんか)
相続税路線価は、国税庁が毎年7月に発表する、道路に面した土地の1㎡あたりの価格です。主に相続税や贈与税の計算基準として使われます。
評価の公平性確保を目的に設定され、公示地価の約80%を目安にしています。これは市場価格の下落リスクを考慮したもので、納税者への過剰な負担を避けるための仕組みです。
⑤ 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)
固定資産税評価額は、市町村(東京23区は東京都)が課税のために算定する価格で、固定資産税や都市計画税などの根拠となります。
公示地価の約70%を目安に設定され、3年ごとに評価替えが行われます。毎年の変動を抑え、安定した課税と行政コストの抑制を図る狙いがあります。
「一物五価」の関係性
公示地価は全ての基本となる「親」のような存在であり、基準地価はそれを補完し、相続税路線価と固定資産税評価額は公示地価を基準に一定の割合を掛けて算出される「子」のような関係にあります。実勢価格はこれらの公的価格を参考にしつつも、最終的には市場のダイナミズムによって決まる階層構造です。
ビジネスの意思決定では、これらの違いを理解し、目的に応じて適切な指標を参照することが不可欠です 。
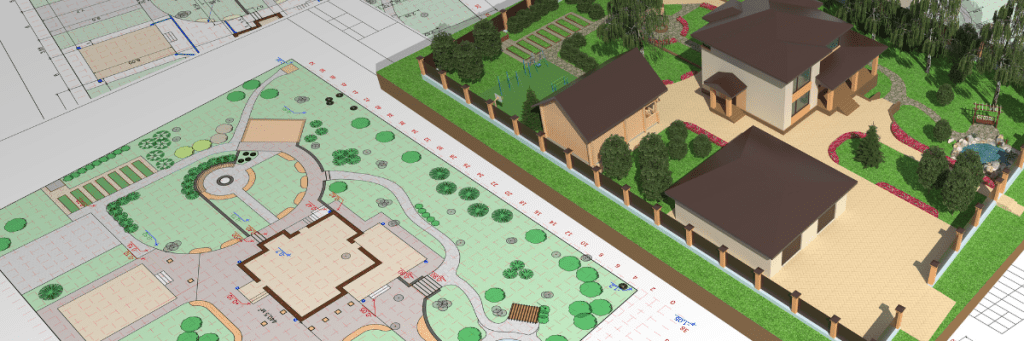
各地価の調べ方:公的データを網羅した地価マップ活用術
土地の5つの価格指標を理解した後に重要なのは、それらの情報を「どこで・どう調べるか」という実践的な知識です。多くの公的価格は、国や自治体のウェブサイトで無料で確認できます。この記事では、代表的な2つの公的地価マップ・データベースの活用方法を具体的に紹介します。
ツール1:国税庁「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
相続税や贈与税の計算に不可欠な「相続税路線価」を調べるための公式ツールです。特に、市街地の土地評価においては基本となる情報源です。
アクセスと基本的な使い方- 1. 国税庁のウェブサイトにある「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のページにアクセスします。
- 2. 日本地図から調べたい都道府県を選択します。
- 3. 次に表示されるメニューから「路線価図」を選びます。
- 4. 市区町村、そして町名を選択していくと、目的の地域の路線価図が表示されます。
ツール2:国土交通省「不動産情報ライブラリ」
「不動産情報ライブラリ」は、地価公示・基準地価・実勢価格などを地図上で一元的に確認できる国交省の公的プラットフォームです。エリア分析の第一歩として、非常に有用なツールです。
https://www.reinfolib.mlit.go.jp/
地価情報のほか、用途地域や防災リスクなどの都市計画情報を地図上で重ねて表示でき、過去の不動産取引価格も確認できるため、実際の相場感をつかむのに役立ちます。また、国勢調査に基づく人口・世帯構成や将来推計人口も閲覧でき、出店エリアの将来性を検討する材料になります。
ただし、これらのデータは複数の省庁に分散しており、更新頻度も年1回など静的です 。リアルタイムの動向は反映されないため、最新の現地情報と併せて使うことが重要です。データの読み解きと判断への活用はユーザーの分析力に委ねられています。これらのツールは「素材」を提供しますが、ビジネスの成果という「料理」を仕上げるには、さらに踏み込んだ分析が不可欠です。
【2025年7月1日発表】最新路線価から読み解く地価の全国動向と経済背景
2025年7月1日に国税庁が発表した最新の相続税路線価は、現在の日本経済と不動産市場の動向を鮮明に映し出す重要なデータです。全国約32万地点の標準宅地の評価額は、前年比で平均2.7%上昇し、4年連続のプラス成長となりました。この上昇率は、現行の算出方法が始まった2010年以降で最大となり、2年連続で過去最高を更新しています。この数字は、日本経済がコロナ禍からの回復基調を確かなものにし、新たな成長フェーズに入りつつあることを示唆しています。

主要なトレンドと地域別の動向
今回の路線価からは、全国一律の回復ではなく、特定の要因に牽引された「選別的な上昇」という構造が見て取れます。
全国的な回復の広がり
まず全体像として、都道府県庁所在地の最高路線価が前年を上回ったのは47都市中35都市にのぼり、横ばいが11都市、下落は鳥取市の1都市のみでした。これは、地価回復の波が三大都市圏だけでなく、多くの地方中核都市にも広がっていることを示しています。
牽引役としての三大都市圏と注目エリア
東京圏:不動のリーダーとして日本全体の地価を牽引しています。特に東京都中央区銀座5丁目の「銀座中央通り(鳩居堂前)」は、1平方メートルあたり4,808万円で40年連続の全国最高値を更新し、前年比+8.7%と力強く伸びました。これはインバウンド需要の完全回復と富裕層の消費活動が背景にあります。池袋駅(+10.4%)や東京駅八重洲口周辺など、大規模再開発進行中のエリアも高い上昇率を記録しています。
大阪圏:
2025年の大阪・関西万博への期待感を背景に、インバウンド観光客の増加が地価を押し上げています。大阪市北区の「御堂筋」は前年比+3.2%の上昇となり、堅調な回復を示しました。
名古屋圏:
名古屋駅前の「名駅通り」が横ばいとなり、他の二大都市圏と比較して成長が一服しました。リニア中央新幹線の開業遅れなどが将来への期待感に影響している可能性があります。
地方のスター都市:
今回の路線価で特に注目すべきは、三大都市圏以外での高い伸びです。埼玉県さいたま市の「大宮駅西口駅前ロータリー」は+11.9%、京都市の「四条通」は+10.6%と、全国でもトップクラスの上昇率を記録しました。これらは、都市再開発や交通インフラの整備が地域の魅力を高め、投資を呼び込んでいる好例と言えます。また、半導体関連工場の進出が期待される地域など、特定の産業投資が地価を押し上げる動きも顕著です。

地価変動の背景にある経済要因
この地価上昇の背景には、複数の経済要因が複雑に絡み合っています。
- 1. インバウンド需要の完全回復と国内観光の活性化: 新型コロナウイルスの5類移行後、訪日外国人観光客は急回復し、2019年を上回るペースで推移しています。
- 2. 都市部の再開発とインフラ整備: 東京や大阪、そして地方中核都市で進行中の大規模な再開発プロジェクトは、新たなオフィスや商業施設、住宅を生み出し、エリア全体の価値と魅力を向上させています。
- 3. 継続的な金融緩和と円安: 日銀による金融緩和政策が継続され、低金利環境が続いているため、企業や個人にとって資金調達が容易な状況です。これが不動産投資を活発化させています。さらに、歴史的な円安は、海外投資家にとって日本の不動産を割安に感じさせ、海外からの投資マネー流入を加速させる一因となっています。
- 4. 資産インフレと建設コストの高騰: 世界的なインフレと資材価格・人件費の上昇は、新築建物の価格を高騰させています。これにより、相対的に中古不動産や土地そのものへの需要が高まり、資産としての価値が見直されています。
これにより、都市部のホテルや商業施設、有名観光地の地価が直接的に押し上げられています。
動向から読み解くべき本質:「二極化」の深化
これらのデータから見えてくるのは、単なる「地価が上がっている」だけではない、日本の不動産市場における「二極化」という構造的な変化です。
全国平均では+2.7%と好調に見えますが、その裏側では、東京の中心部や再開発が進むエリア、インバウンド需要のある観光地など一部の地域が大きく伸びる一方で、地方都市の多くでは地価が横ばい、あるいは下落しています。鳥取市のように最高路線価が下落した都市や、山形市・水戸市のように横ばいだった都市はその象徴です。
この二極化の傾向は、「2025年問題」に代表される人口構造の変化によって、今後さらに進むと考えられます。団塊の世代が後期高齢者となり相続によって不動産の供給が増える一方、地方では人口減少が続き、買い手がつかず空き家が増加し、結果として地価の下落圧力が強まることが予想されます。
ビジネスの意思決定において、この二極化の示唆は非常に重要です。「全国的に地価が上昇している」という全体の傾向だけを見て投資判断を下すのはリスクが高いと言えるでしょう。自社のターゲットエリアが二極化のどちらに位置しているのか、成長を支える要素(再開発、観光、産業集積など)が存在するのかを細かく見極めることが、持続的な成果につながります。
このような精緻なエリア分析の必要性こそが、「地価マップを見るだけ」では得られない、次のステップへと進む鍵となります。
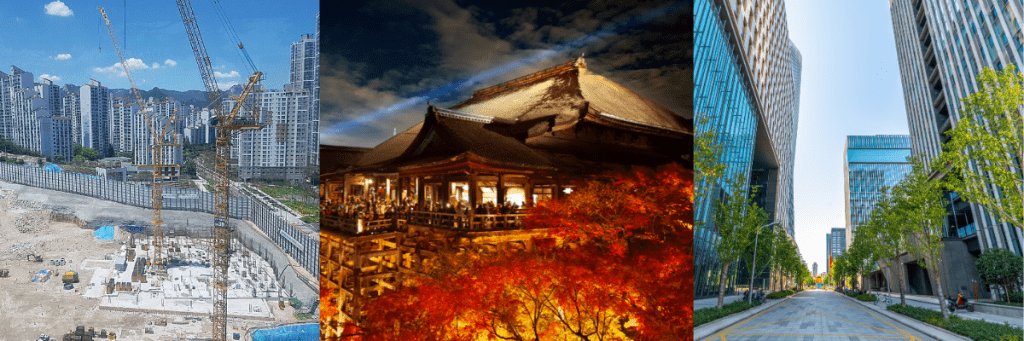
地価データ活用の落とし穴:なぜ「地価が高い=儲かる」ではないのか?
地価マップは事業計画に活用されますが、「地価が高い=ビジネスに向いていて儲かる場所」と早計に判断するのは危険です。この章では、その考え方がなぜ危ういのかを、「コスト」「競争」「顧客」の3つの視点から掘り下げます。地価データを意味ある戦略へと昇華させるためには、この落とし穴を理解することが重要です。
議論1:地価は「成功の指標」ではなく「コスト変数」である
多くの人が地価をエリアの魅力や価値の指標と見がちですが、実際にはビジネスにおけるコストの一部です。地価が高ければ、土地取得費や賃料が上がり、初期投資も重くなります。加えて、地価に連動する固定資産税も大きな負担となります。特に商業地では軽減措置が少ないため、所有しているだけで多額のコストが発生します。
つまり、高地価エリアでの出店は、それに見合う売上が見込める確かな根拠がなければ、大きな経営リスクになりかねません。
議論2:地価は「過去の結果」であり「現在の競争環境」を語らない
地価データは、あくまで年1回のスナップショットであり、過去の評価にすぎません。市場は常に動いており、地価が高い=今も優位とは限らないのです。むしろ、人気エリアはすでに多くの競合が集まっており、競争の激しい「レッドオーシャン」である可能性も。地価マップでは、競合の数やシェアなど、実際のビジネス環境は見えてきません。
議論3:ビジネスの成功を左右する「本当の主役」は地価マップには載っていない
最終的に収益を生み出すのは土地ではなく顧客です。重要なのは、「どんな人がどれだけ住んでいるか」「どう動いているか」「アクセスに障壁はないか」といった顧客視点の情報です。これらの情報は、いくら地価マップを見ても得られません。
つまり、地価マップが教えてくれるのは主に「コスト」の一部であり、「収益」に関わる情報はブラックボックスです。片目だけで物事を判断するようなものであり、正確な意思決定には、顧客動向や人流などの多面的なデータを踏まえた分析が不可欠です。

商圏分析GIS:地価マップを超えた、データドリブンな意思決定
地価マップだけに頼ったエリア戦略の限界とリスク(高コスト、激しい競争、顧客情報不足)を乗り越えるために注目されているのが、「商圏分析GIS(地理情報システム)」です。
GISとは、さまざまなビジネスデータを地図上で一元的に見える化し、分析できる「賢い地図システム」です 。Excelの表や数値だけでは把握しにくい地域ごとの特性や顧客の広がり、競合との位置関係などを、地図上で直感的に把握できるようになります。
ここでは、従来の地価マップとGISの違いに触れながら、GISがビジネスにもたらす新たな可能性を具体的な活用シーンを交えて解説します。
GISがもたらす3つの変革
GISは単なる地図ソフトではなく、「統合」「可視化」「分析」の3つの機能を通じて、エリア分析を根本から変えます。
データの統合(Integration)
GISの大きな強みは、多様なデータを一つの地図上に重ねて扱える点です。地価公示や路線価などの公的データはもちろん、国勢調査による人口統計、自社の顧客情報、競合店の位置、人流データまで、あらゆる情報を一元的に管理できます。
パターンの可視化(Visualization)
大量の顧客リストを表で眺めても傾向は掴みにくいものですが、GISで地図にプロットすれば、「この通りを越える来店客は少ない」「この駅周辺に優良顧客が集中している」といったリアルな商圏の姿が一目でわかります。視覚的な把握は、課題やチャンスの発見につながります。
高度な分析(Analysis)
GISは地図上にデータを表示するだけでなく、分析も可能です。たとえば「500m圏内のターゲット人口と競合数を自動計算」「好調な店舗の商圏特性をもとに未出店エリアを抽出」といった高度な分析を、専門知識がなくてもスピーディに行えます。
地価ポテンシャルデータ
当社のGIS「MarketAnalyzer® 5」では、標準搭載の統計データに加え、より高度な分析を可能にする独自データも利用できます。代表例が「地価ポテンシャルデータ」です。
→データの活用例や詳細はこちら:https://www.giken.co.jp/datalineup/statistics/land-price/
これは、公的な地価調査の「点」データをもとに、独自のアルゴリズムで全国を500mメッシュや町丁目単位の「面」で推計した平均地価データベースで、公的調査がない地域も含めて日本全体の地価水準をシームレスに把握できます。
このデータは他のビジネス情報と組み合わせて効果を発揮します。たとえば、新規出店候補地の「人口(売上ポテンシャル)」と「地価ポテンシャル(賃料目安)」を同時に地図上で比較でき、「人口は多いが地価も高いエリア」や「人口多く地価割安な“お宝エリア”」を戦略的に見つけられます。
また、既存店の評価にも有効です。店舗ごとの「売上」「商圏人口」「地価ポテンシャル」をスコア化し比較することで、課題が明確になります。例えば「人口ポテンシャルは高いが売上が低迷、かつ地価が高い」店舗では、販促強化やよりコスト効率の良いエリアへの移転など、データに基づく具体的な対策検討が可能になります。
マーケティングGIS「MarketAnalyzer® 5」の無料トライアル
GISがどんなシステムか、どんなことができるのか、ご興味のある方は無償提供がおすすめです。
GISをいきなり導入するのはハードルが高いと感じるかもしれません。まずは、無償で提供されているGISソフトをお試しください。
まとめ
本コラムでは、「地価マップ」を起点に、土地価格の仕組みから最新市場動向、そして専門的なエリア分析手法までを詳しく解説しました。
まず、一つの土地に5つの価格が存在する「一物五価」の仕組みとそれぞれの意味を学び、2025年7月の最新路線価データからは、都市部と地方で進む地価の「二極化」という構造的変化を読み解きました。
また、ビジネス判断において地価はあくまでコストの一要素であり、「地価が高い=儲かる」という単純な図式は成り立たないことを示しました。成功には、顧客や競合、地理条件など多様な要因を統合的に分析することが欠かせません。
公的な地価マップや不動産情報は静的で分断された情報にとどまり、ここに商圏分析GISが解決策として登場します。GISは地価や人口、顧客、競合などのデータを地図上に重ねて視覚化・分析し、科学的な意思決定を支援します。
当社のマーケティングGIS「MarketAnalyzer® 5」は、新規出店候補地のポテンシャル予測から既存店の売上改善、販促エリアの最適化まで、多角的にエリア戦略をサポートするプロ仕様のツールです。
知識を得るだけでなく、実際に使って体感することで、地価マップの先にあるデータドリブンな意思決定の価値を実感いただけます。

監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |
|
| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |
 |
電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)
Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/