
エリアマーケティングラボ
住宅リフォーム需要と市場分析
~データで勝つリフォーム事業戦略~
2025年6月30日号(Vol.155)
はじめに
現在の住宅リフォーム市場は、安定と変化のまさに狭間にいます。短期的には、コロナ禍で生まれた「巣ごもり需要」の反動で、市場は一時的に落ち着く局面を迎えています。しかし、長期的に見れば、その基盤は非常に強固です。日本の住宅市場が成熟期を迎え、膨大な数の住宅が必然的に古くなっていくという、避けられないトレンドが、安定した需要をしっかり支えているからです。
本コラムでは、これらの状況を踏まえ、まずリフォーム市場の規模を複数のデータから定量的に分析し、短期・長期の将来予測を提示します。次に、お客様のニーズの変化から生まれる新しい事業機会について詳しく解説します。
さらに、GISを活用した商圏分析・エリアマーケティングの実践手法を、先進企業の事例を交えながら具体的に解き明かしていきます。
住宅リフォーム事業に携わる経営者、マーケティング責任者、そして事業開発担当者の皆さんに向けて、市場のリアルなデータ、業界が直面する構造的な課題、そして最新のエリアマーケティング手法を総合的に分析し、不確実な時代を乗り越え、持続的に成長するためのヒントをお届けします。
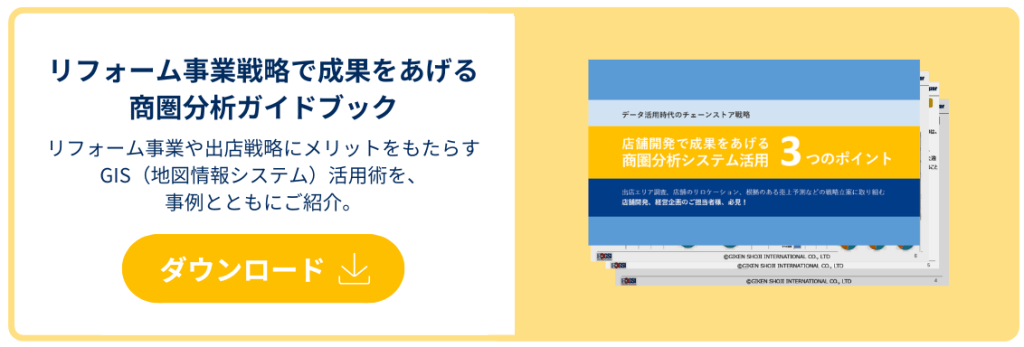
住宅リフォームの市場規模と将来予測
リフォーム市場規模の現状と推移
住宅リフォーム市場の規模を正確に把握することは、事業戦略を立てる上での第一歩です。しかし、その数値は調査機関や定義によって異なるため、多角的な視点で理解することがとても大切です。
主要な調査機関のデータを見ると、2023年の市場規模についてはいくつかの見解があります。株式会社矢野経済研究所の推計によれば、2023年の住宅リフォーム市場規模は前年比0.6%増の7兆3575億円(約7.4兆円)に達しました。
このわずかな増加は、コロナ禍で高まった住環境への関心の継続と、資材費・人件費の上昇に伴うリフォーム工事単価の上昇が背景にあると分析されています。
一方で、公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターの集計では、2023年の市場規模は7兆100億円とされています。
さらに、リフォーム産業新聞社は同年の市場を約6.2兆円と推計しており、各機関の間に数十億円から1兆円以上の差が見られます。
この数値の差異を理解する上で非常に重要なのが、「広義」と「狭義」の市場定義です。
一般的に、狭義のリフォーム市場とは、国土交通省の住宅着工統計における「増築・改築工事費」と「設備等の修繕維持費」を合計したものを指します。これは、リフォーム事業者が直接手掛けるコアな工事領域と捉えられます。
対して、広義のリフォーム市場は、この狭義の市場規模に「エアコンや家具、インテリア商品等のリフォームに関連する耐久消費財の購入費」を加えたものです。2023年においては、狭義の市場が7兆100億円であるのに対し、広義の市場は8兆2500億円と、その差は約1.2兆円にもなります。
この定義の違いは、単なる統計上の分類にとどまりません。リフォーム事業者にとって、この約1.2兆円の差額は、事業拡大の可能性を秘めた隣接市場を意味します。例えば、コアなリフォーム工事を請け負う企業が、インテリアコーディネートサービスや提携する家具・家電メーカーの商品をセットで提案することで、顧客単価の向上と新たな収益源の確保を狙うことができます。
自社の事業領域がどちらの定義に近いか、そして隣接市場をどのように攻略するかを考える上で、この差異の認識は戦略的な羅針盤となり得ます。
市場全体の動向としては、過去10年間にわたり6兆円から7兆円台の規模で安定的に推移しており、コロナ禍のような大きな外部環境の変化に対しても強い耐性を示してきたことが特徴です。これは、住宅が生活に必須のインフラであり、経年劣化による修繕・改修需要が常に底堅く存在することを示唆しています。
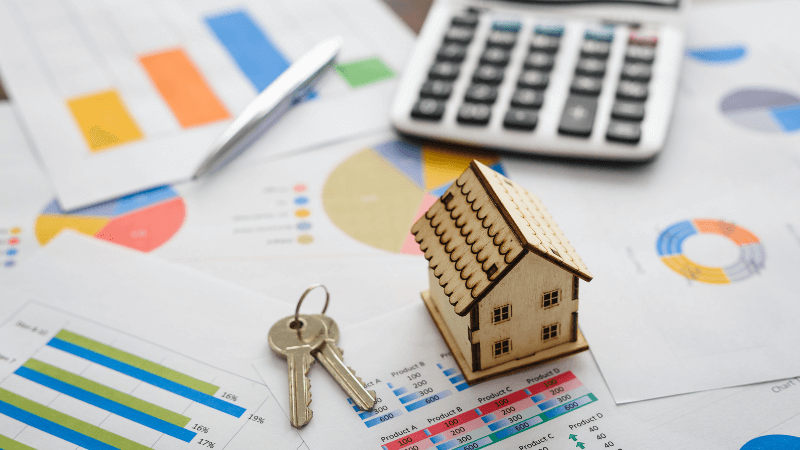
リフォーム市場予測:短期・長期の展望
市場の将来を見通すには、短期的な変動要因と長期的な構造トレンドを分けて考える必要があります
短期予測(2024年):一時的な縮小局面へ
2024年の市場については、一時的な縮小が予測されています。矢野経済研究所は、2024年の市場規模を前年比3.2%減の7.1兆円と予測しています。この主な要因は、コロナ禍における在宅時間の増加によって喚起され、一部前倒しで実施されたリフォーム需要の反動減です。多くの家庭で必要とされていた改修が一巡し、需要が一時的に落ち着くと見られています。
しかし、これは市場の衰退を意味するものではありません。資材費や人件費の高騰を背景に、リフォーム工事の単価は引き続き上昇傾向にあるため、需要の減少分をある程度相殺し、市場規模の大幅な落ち込みには至らない見込みです。
この短期的な調整は、過熱した市場が健全な状態に戻るプロセスと捉えることができます。
長期予測(〜2040年):ストック型社会への移行がもたらす巨大な商機
短期的な調整とは対照的に、長期的な展望は非常に明るいと言えます。株式会社野村総合研究所は、広義のリフォーム市場が今後も着実な成長を続け、2040年には8.9兆円に達するとの予測を発表しています。この力強い成長の根幹をなすのは、新設住宅着工戸数の減少というトレンドとは裏腹に、日本の社会構造そのものが「フロー(新築)型」から「ストック(既存住宅)型」へと移行している事実にあります。この移行を牽引するのは、日本の膨大な「住宅ストックの高齢化」です。
■ リフォーム適齢期住宅の激増
築40年以上の住宅が今後急増し、構造的な耐久性や設備の全面的な見直しを要する大規模改修、あるいは建て替えを検討する時期を迎えます⁵。特に、1981年以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅は、防災の観点からも改修が急務です。
また、1991年〜2000年に建てられた約1047万戸の住宅は、キッチン・バスなどの設備交換や外壁・屋根塗装といったメンテナンスの適齢期を迎えており、巨大な潜在需要を形成しています。
■ 平均築年数の延伸
住宅ストック全体の平均築年数は、2013年度の22年から2040年度には33年近くまで延びると予測されており、維持・修繕の必要性が必然的に増大します。これは、一過性のブームではなく、構造的かつ不可逆的な需要の源泉です。
この長期的な成長トレンドは、リフォーム事業のマーケティング戦略に根本的な転換を迫ります。もはや「新しいライフスタイルの提案」といった新築市場に近い訴求だけでは不十分です。
これからは、「住宅性能の回復・向上(耐震、断熱)」「長期的な資産価値の維持・向上」といった、既存ストックの価値を最大化するコンサルティング的なアプローチが求められます。これは、より技術的で、お客様の不安や経済的合理性に寄り添う、専門性の高い営業・マーケティング活動へのシフトを意味します。
さらに、社会課題として注目される空き家問題も、リフォーム市場にとっては新たな成長分野となります。2043年には日本の空き家率が約25%に達し、特に腐朽・破損のある管理不全な一戸建て空き家が2023年の2倍以上になると予測されています。
これは、空き家を再生し、賃貸物件や売却物件として市場に再流通させる「空き家再生リノベーション」という巨大なビジネスチャンスを生み出しています。

リフォーム需要の最新動向と事業機会
安定した成長が見込まれるリフォーム市場で勝ち抜くためには、マクロな市場規模だけでなく、消費者の価値観やライフスタイルの変化によって生まれる「需要の質的変化」を的確に捉えることが不可欠です。
現在、リフォーム需要は大きく4つのトレンドに集約されつつあり、それぞれが新たな事業機会を示唆しています。
トレンド1:省エネ・性能向上リフォームの主流化
かつては一部の意識の高い層の選択肢であった省エネリフォームが、今や市場の主流となりつつあります。この背景には、規制、経済性、政策という3つの強力な推進力があります。
背景
2025年4月から原則すべての新築・増改築で省エネ基準への適合が義務化される規制強化、近年のエネルギー価格の高騰による光熱費削減ニーズの切実化、そして「住宅省エネ2024キャンペーン」に代表される政府の強力な補助金制度が、消費者の背中を大きく押しています。具体的な需要
・ 断熱リフォーム日本の既存住宅の多くは断熱性能が低く、冬の寒さや夏の暑さに悩む家庭は少なくありません。断熱性能の向上は、快適性の向上だけでなく、光熱費の削減に直結します。さらに、断熱不足は壁内結露を引き起こし、カビの発生や木材の腐朽に繋がり、住宅の寿命そのものを縮める根本的な問題です。このため、窓の交換(内窓設置や複層ガラス化)、外壁や屋根への断熱材追加といった工事への本質的なニーズは極めて高いと言えます。
・ ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)化
高断熱化に加え、太陽光発電システムや高効率な設備を導入し、エネルギー収支をゼロ以下にするZEHへの関心も高まっています。補助金制度をフックに、将来の資産価値向上も見据えたZEHリフォーム提案は、他社との強力な差別化要因となります。
・ 高機能・高耐久商材へのシフト
初期費用は高くとも、長期的なメンテナンスコストを削減できる製品への需要が拡大しています。例えば、耐用年数が長い高耐久塗料による外壁塗装や、軽量で耐震性向上にも寄与し、錆びにくい金属屋根材への葺き替えなどがその代表例です。
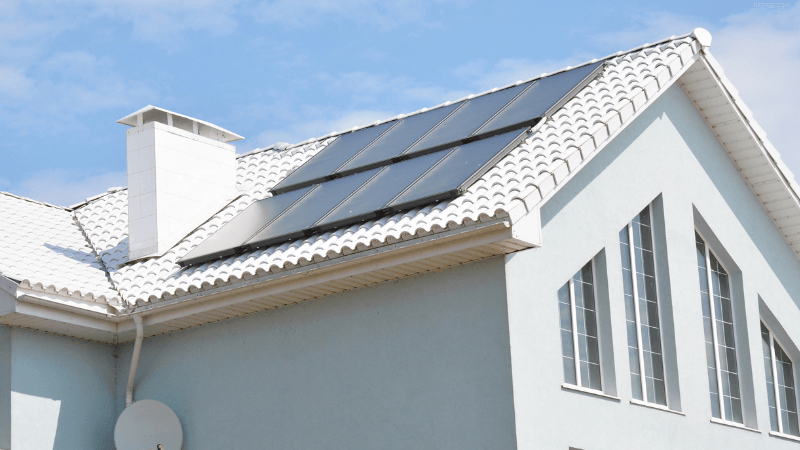
トレンド2:ストック活用とライフスタイル変化への対応
新築住宅の価格が高騰し続ける中、消費者の目は既存の住宅ストックへと向かっています。
「中古購入+リノベーション」の定着
比較的安価な中古住宅を購入し、自分たちのライフスタイルに合わせて間取りや内装を全面的に刷新する「中古購入+リノベーション」は、もはや一過性のブームではなく、住宅取得の主要な選択肢として完全に定着しました。これはリフォーム事業者にとって、単発の改修工事に留まらない、大規模かつ高単価なプロジェクトを獲得する最大の事業機会の一つです。このトレンドは、単に消費者向けのマーケティング活動だけでなく、新たなビジネスエコシステムの構築を促します。
住宅購入の最初の接点となるのは不動産仲介会社であり、顧客が物件を探す段階でいかにリフォーム会社と接点を持てるかが勝負の分かれ目となります。
つまり、不動産仲介会社との強固なパートナーシップを構築し、物件紹介とリフォーム提案をワンストップで提供できる体制を築くことが、この市場を制する鍵となります。
コロナ禍が促した住まい意識の変化
パンデミックによる在宅時間の増加は、人々の住まいに対する価値観を恒久的に変化させました。自宅が単なる休息の場から、仕事、学習、娯楽の場へと多機能化したことで、ワークスペースの新設、オンライン会議のための間仕切り設置や防音工事といった、具体的な内部改修の需要が顕在化しました。
また、「おうち時間」をより豊かに過ごしたいという意識が高まり、庭付きの戸建てへの関心が増したり、より快適な空間を求めてインテリアや設備への投資意欲が向上したりする傾向が見られます。
デザイン性の追求
機能性や価格だけでなく、「自分らしさ」を表現できるデザインへの要求水準が高まっています。北欧風、インダストリアル、和モダンといった特定のデザインテイストの実現や、タイルやウッドパネルを用いたアクセントウォール、空間を広く見せるアイランドキッチンや吹き抜けなど、個性的でおしゃれな空間を求めるニーズは、特にリノベーション市場で顕著です。
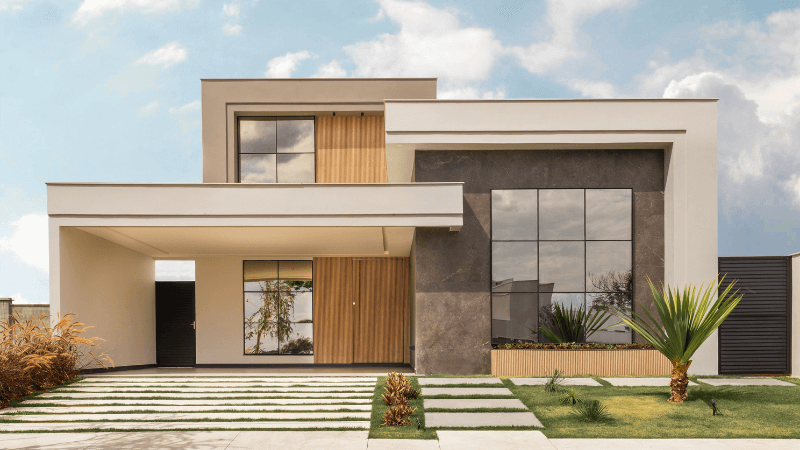
トレンド3:社会構造の変化がもたらす需要
日本の人口動態や地理的特性といったマクロな変化も、新たなリフォーム需要を生み出しています。
高齢化と介護・バリアフリーリフォーム
2025年には「団塊の世代」が全員75歳以上の後期高齢者となり、医療・介護需要が急増する「2025年問題」が目前に迫っています。住み慣れた自宅で暮らし続けたいと願う高齢者が増える中、在宅介護を支えるための住宅改修は不可欠です。
手すりの設置、床の段差解消、和式トイレから洋式トイレへの交換といった比較的小規模なバリアフリー工事の需要が、今後確実に増加していきます。
防災意識の高まりと耐震リフォーム
能登半島地震をはじめとする大規模災害の頻発を受け、国民の防災意識、特に住宅の耐震性に対する関心は非常に高まっています。特に、現行の耐震基準を満たしていない1981年以前の住宅や、築40年以上が経過し耐震性に不安のある住宅を対象とした耐震診断や補強工事は、生命と財産を守るための喫緊の課題として認識されており、潜在的な需要は大きいと言えます。
トレンド4:テクノロジーとの融合
住宅とテクノロジーの融合は、リフォーム市場に新たな価値とビジネスモデルをもたらしています。
スマートホーム・IoTリフォームの成長
スマートフォンから遠隔で施錠・解錠できるスマートロック、音声で操作できる照明やエアコン、家庭内のエネルギー使用量を可視化・最適化するHEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)など、IoT技術を活用した住宅設備の導入が、リフォームの一分野として確立しつつあります。これらは利便性や防犯性の向上、省エネへの貢献だけでなく、高齢者の見守り機能としても期待されており、幅広い層に訴求できる可能性を秘めています。
AI(人工知能)の活用
AIの活用は、お客様向けサービスの高度化と、事業者側の業務効率化の両面で進んでいます。設計分野では、お客様の要望を入力するだけで複数のデザインプランや3Dパースを自動生成するシステムが登場しています。また、過去の膨大な見積もりデータを学習させることで、見積もり算出を自動化・高速化する取り組みも始まっています。
さらに、介護リフォームで必須となる煩雑な行政への申請書類作成をAIが支援するサービスも実用化されており、バックオフィス業務の負担を軽減し、本来注力すべき営業や施工管理にリソースを集中させることが可能になっています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
これらのトレンドから見えてくるのは、リフォーム需要が二極化しているという事実です。
一つは、耐震、断熱、バリアフリーといった「生命・財産・健康を守るための必須の性能向上(Essential Performance Upgrades)」であり、もう一つは、デザイン、趣味の空間、スマートホーム化といった「暮らしを豊かにするための選択的なライフスタイル向上(Discretionary Lifestyle Enhancements)」です。
前者は不安解消や経済的合理性といった論理的な判断が、後者は憧れや自己実現といった感情的な満足が購買動機となります。したがって、リフォーム事業者は、この二つの異なるニーズに対して、それぞれに最適化されたマーケティングメッセージと提案アプローチを使い分ける、二刀流の戦略が求められます。
リフォーム業界が直面する構造的課題と戦略的対応
長期的な成長が見込まれる一方で、リフォーム業界は深刻な構造的課題に直面しています。これらの構造的な問題に対し、業界全体で戦略的な対応が求められています。
【課題1】深刻化する人手不足と職人の高齢化
リフォーム業界は、建設業界全体を覆う深刻な人手不足問題の直撃を受けています。特に、2024年4月から適用が開始された時間外労働の上限規制、いわゆる「建設業の2024年問題」は、労働力確保を一層困難にしています。
この問題の根は深く、単なる労働時間の制約に留まりません。業界の担い手である職人の高齢化が著しく、若手の入職者が少ないため、熟練の技術やノウハウの継承が断絶の危機に瀕しています。
リフォーム工事の品質は、現場の職人の腕に大きく依存するため、技術力のある人材の不足は、そのまま施工品質の低下に直結しかねません。
また、一人前の職人を育成するには長い下積み期間が必要であり、即戦力の確保は極めて困難な状況です。この人手不足が、後述する工期の長期化や人件費高騰の根本的な原因となっています。
【課題2】止まらない資材・人件費の高騰
2021年頃からの「ウッドショック」に端を発し、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格や木材供給網の混乱、世界的なインフレ、そして円安が複合的に絡み合い、建築資材の価格はかつてないレベルで高騰し、高止まりしています。
ある調査では、2021年1月から2024年2月までの期間で、主要な建設資材の価格が約30%も上昇したと報告されています。
このコスト上昇は、リフォーム費用に直接転嫁せざるを得ません。持ち家のリフォーム費用は、2020年と比較して平均で15%前後も上昇しており、お客様が見積もりを見て「何かの間違いでは」と驚くケースも少なくありません。
これにより、お客様が当初の予算をオーバーしてしまい、工事内容の縮小や計画そのものの中心に至る、あるいは費用を巡るトラブルに発展するといった問題を引き起こしています。
【課題3】戦略的対応
これらの構造的課題に対して、企業は戦略的な対応を迫られています。
DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進
人手不足を補い、生産性を向上させるために、テクノロジーの活用は不可欠です。例えば、ドローンを活用した屋根や外壁の現況調査、AIによる見積もり作成の自動化、施工管理アプリによる情報共有の効率化など、デジタル技術を導入することで、限られた人員でより多くの業務をこなすことが可能になります。
付加価値提案による価格競争からの脱却
コストが上昇し続ける中で、安売り競争に陥ることは自殺行為です。重要なのは、価格以上の価値をお客様に提供し、納得してもらうことです。例えば、省エネ性能の向上による将来の光熱費削減効果をシミュレーションして提示する、優れたデザイン力で顧客の夢を形にする、長期的なアフターサービスや保証で安心感を提供するなど、独自の付加価値を明確に打ち出し、適正な価格で受注できるブランド力と提案力を構築することが求められます。
M&Aによる業界再編への対応
厳しい経営環境の中、業界再編の動きも活発化しています。大手ハウスメーカーや異業種の企業が、リフォーム市場への参入・拡大を狙って、実績のあるリフォーム会社を買収するケースが増えています。独立を維持するだけでなく、大手グループの傘下に入ることで、資金力やブランド力、人材確保といった経営基盤を強化し、成長を目指すという選択肢も現実的な戦略となっています。
データで勝つリフォーム事業戦略
GISによる商圏分析・エリアマーケティングの実践
市場が成熟し、コスト上昇と規制強化という逆風が吹く中、リフォーム事業者が持続的成長を遂げるためには、事業運営のあり方を根本から見直す必要があります。その核心となるのが、データに基づいた科学的な意思決定、すなわち「データドリブン経営」への転換です。
なぜ今、リフォーム業界にGISの活用が不可欠なのか
従来、リフォーム会社の集客活動は、営業担当者の「勘と経験」に頼る部分が多くありました。
特定のエリアへのチラシのポスティング、新聞折り込み、地域イベントでのブース出展などがその代表例です。これらの手法は地域密着型ビジネスにおいて依然として有効な場面もありますが、誰に届いているのか、どれほどの効果があったのかを正確に測定することが難しく、非効率な販促活動になりがちでした。
限られた予算と人員というリソースを、最も受注確度の高いエリア、そして最も利益率の高い顧客層に集中投下することが、これまで以上に重要になっています。
これを実現する強力な武器が、GIS(Geographic Information System:地理情報システム)です。
GISとは、地図データの上に、人口、世帯、年収、住宅の種類といった様々な統計データを重ね合わせ、それらを地図上で色分けするなどして視覚的に表示・分析するためのツールです。これにより、「どこに、どのような特徴を持つ人々が、どのような家に住んでいるのか」という商圏の姿を、誰もが一目瞭然で、かつ直感的に把握することが可能になります。
リフォーム業界においてGISがもたらす価値は計り知れません。
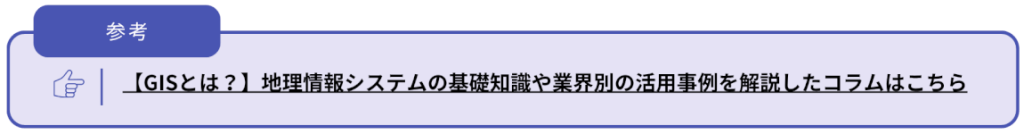
商圏の可視化とポテンシャル把握
自社の既存顧客がどのエリアに集中しているのか、逆に手薄になっているエリアはどこか、競合他社はどのエリアに強いのか、といった商圏全体の状況を地図上で可視化できます。これにより、自社の強みと弱み、そして未開拓の有望エリアを客観的に把握できます。販促活動の最適化
例えば、「店舗から車で20分圏内で、築30年以上の一戸建て持ち家が多く、かつ世帯年収が800万円以上のエリア」といった具体的な条件でターゲットエリアを絞り込むことができます。そのエリアに限定して外壁・屋根リフォームの高品質な提案チラシをポスティングすることで、無駄な広告費を大幅に削減し、費用対効果を最大化することが可能です。客観的根拠に基づく意思決定
新規の営業所出店や、大規模な販促キャンペーンの企画といった重要な経営判断において、GISによる分析データは強力な客観的根拠となります。「このエリアは潜在顧客数が多く、競合も少ないため、出店成功の確率が高い」といったロジカルな説明は、社内の合意形成を円滑にし、投資の失敗リスクを低減させます。【実践ガイド】GISを活用したリフォーム潜在顧客の発掘・分析手順
GISと各種エリアデータを組み合わせることで、リフォームの潜在顧客を段階的に、かつ高精度に絞り込むことができます。以下にその具体的な手順を示します。
【STEP1】基礎分析: ターゲットエリアの物理的・人口動態的特性を把握する
まず、自社の商圏がどのようなエリアなのか、その基本的な特性を把握します。・使用データ
国勢調査に基づくデータ(総人口、年齢構成、世帯構成など)、住宅・土地統計調査に基づくデータ(住宅の建て方(一戸建て/共同住宅)、所有関係(持ち家/借家)など)。
・分析例
自社店舗を中心とした半径3km圏内を商圏と設定します。GIS上でこの商圏内の町丁目ごとに、「持ち家・一戸建て」の世帯数が多いエリアを濃い色で、「65歳以上の高齢者人口」が多いエリアを別の濃い色で表示させます。
この二つの色が重なるエリアは、「住宅の意思決定権を持ち、かつバリアフリーリフォームの潜在ニーズが高い世帯」が集中している可能性が高いと仮説を立てることができます。
【STEP2】深掘り分析:「築年数データ」でリフォーム適齢期住宅を狙い撃つ
次に、リフォームの発生確率が最も高い「リフォーム適齢期」の住宅を特定します。▼ 使用データ
住宅の建築時期別のストック数がわかる「築年数データ」
www.giken.co.jp/datalineup/statistics/chikunensu/
・ヒートマップ作成
【STEP1】で大まかに特定したエリアに対し、さらに条件を絞り込みます。例えば、「1981年〜2000年に建築された持ち家一戸建て」が密集するエリアをGIS上で赤くハイライトさせます。
この年代の住宅は、外壁塗装、屋根のメンテナンス、水回り設備の交換といった、築25年〜40年で発生しやすいリフォームのまさに一次ターゲットです。
・クロス分析
ここからがGISの真骨頂です。上記の「リフォーム適齢期住宅が密集するエリア」の地図に、統計データから推計した「過去10年間に水回りのリフォーム履歴がない世帯」のデータを重ね合わせます。
すると、「リフォームの必要性が高い時期に来ているにもかかわらず、まだ実施していない」という、最も確度の高いホットな潜在顧客が集中する町丁目が、例えば青色などで浮かび上がってきます。
・アクション
このようにしてピンポイントで特定されたエリアに対し、「水回りリフォーム無料相談会」や「最新節水トイレ・システムキッチン展示会」といった、具体的なテーマを掲げた告知チラシを集中投下します。これにより、関心のないエリアへの無駄な配布をなくし、反響率を劇的に高めることが期待できます。
【STEP3】ペルソナ分析:「サイコグラフィックデータ」で顧客の心に響くメッセージを作る
ターゲットエリアを特定しても、そこに住む人々の価値観やライフスタイルを理解しなければ、心に響くメッセージは届けられません。・デモグラフィックの限界
年齢や年収、家族構成といった「デモグラフィックデータ」だけでは、お客様の本当の姿は見えません。
同じ「40代、年収1000万円、子供2人」の男性でも、一方は「価格と機能性重視」、もう一方は「デザインと環境性能重視」かもしれません。お客様が「なぜ(Why)」その商品を買うのか、その背景にある心理を理解することが、成約率を高める鍵となります。
・使用データ
この「なぜ」を解き明かすのが、価値観、ライフスタイル、趣味嗜好といった心理的属性を示す「サイコグラフィックデータ」です。
技研商事インターナショナル社が提供するクラウド型GISとエリアデータ「c-japan®」や「Psycho-Demo-Geo(Consumer Lifestyle Data)」のようなデータ製品は、国勢調査などではわからない住民のライフスタイル意識(例:健康志向、エコ意識、デザインへの関心度)や購買意欲を、町丁目などの細かいエリア単位で可視化します。
・分析例
【STEP2】で特定したホットなエリアに、このサイコグラフィックデータを重ね合わせます。もしそのエリアの住民が、「健康志向が強く、自然素材への関心が高い」という特性を持つことがデータで示されたとします。
・アクション
その場合、チラシやウェブサイトで訴求するメッセージを、単なる「最新設備の特価キャンペーン」から、「無垢材や珪藻土を使った、家族の健康を守る自然素材リフォームで、日々の暮らしをより豊かにしませんか?」といった、彼らの価値観に寄り添ったものへと変更します。
さらに、そのエリアにターゲティングしたWeb広告を配信し、専用のランディングページへ誘導することで、より深い共感を呼び、問い合わせに繋げることができます。
【パナソニック ハウジングソリューションズ様】GIS戦略と「c-japan®」の活用事例
データ活用の効果を具体的に理解するために、業界の先進企業であるパナソニックハウジングソリューションズ様の事例を見てみましょう。同社は、リフォーム事業のフランチャイズチェーンである「パナソニックのリフォーム」の加盟店サポートに、クラウド型GISとエリアデータ「c-japan®」を導入しています。
■ 直面していた課題
・分析環境の制約
従来使用していたインストール型のGISでは、特定のPCでしか分析ができず、担当者が限られていました。これにより、在宅勤務といった多様な働き方への対応が難しく、分析業務の属人化も課題でした。
・ターゲット理解の浅さ
既存のGISでは、商圏内にターゲット層が「どれくらいいるか」という量的な分布は把握できても、その人々が「どのような価値観やライフスタイルを持つのか」という質的なペルソナ(人物像)までは見えませんでした。■ 導入後の成果
・客観的データに基づく加盟店サポートの実現
クラウドGISの導入により、スーパーバイザー(SV)は場所を選ばずに商圏分析レポートを作成できるようになりました。
これにより、SV個人の主観や経験則ではなく、データという客観的根拠に基づいた説得力のある経営アドバイスを加盟店に提供できるようになりました。
このデータドリブンなサポートは、加盟店からも「自社の経営を論理的に見極める手段」として高く評価され、チェーン全体の競争力向上に繋がっています。
・「c-japan®」によるターゲットの具体化
居住者をライフスタイルや価値観で32のセグメントに分類するデータ「c-japan®」を活用することで、ターゲットの解像度が飛躍的に向上しました。
「どこに、どれくらいのターゲットがいるか」だけでなく、「その層はどのような人々か」までを具体的に把握できるようになったのです。
これにより、各加盟店は自らの商圏特性に合わせ、より的確な販促コンセプトやキャンペーンテーマを設定することが可能になりました。
▶ 「c-japan®」の詳細はこちら
・新規加盟店開発への応用
加盟店サポートに留まらず、GISは新規出店戦略にも活用されています。自社の契約データや各種統計データをGIS上で分析し、リフォーム需要のポテンシャルが高いにもかかわらず、まだ加盟店が出店していない「空白の有望エリア」を特定。
これにより、客観的なデータに基づいて出店候補地を選定し、社内での承認プロセスも円滑に進めることができるようになりました。
▶ パナソニックハウジングソリューションズ様のGIS導入事例全文はこちら
このパナソニックの事例は、GISの導入が単なる「ツールの導入」ではなく、事業全体の「文化の変革」であることを示唆しています。それは、個々の営業担当者の勘や経験に依存する「セールスドリブン」な組織から、中央のマーケティング・戦略部門がデータを分析し、現場の活動を科学的に方向付ける「マーケティングドリブン」な組織へと進化するプロセスです。この変革を成功させることが、データ時代のリフォーム業界で勝ち残るための必須条件と言えるでしょう。
まとめ
本コラムで詳しく見てきたように、日本の住宅リフォーム市場は、短期的な需要の揺り戻しという調整局面を経つつも、国内の膨大な住宅ストックの高齢化という巨大で避けられない追い風を受け、長期的には安定した成長軌道に乗っています。しかし、その恩恵を手にすることができるのは、時代の変化にうまく適応できた事業者だけです。
これからのリフォーム事業者に求められるのは、単なる「工事業者」としての役割ではありません。お客様一人ひとりのライフステージや価値観に寄り添い、住宅という最も重要な資産の価値を、性能・快適性・安全性のすべての面から長期的に向上させていく「住まいの総合コンサルタント」としての役割です。
そこではデータに基づく市場分析と戦略立案が、不可欠です。
この情報が、皆さんのビジネス戦略の一助となれば幸いです。さらなる詳細や具体的なご相談が必要な場合は、いつでもお問い合わせください。
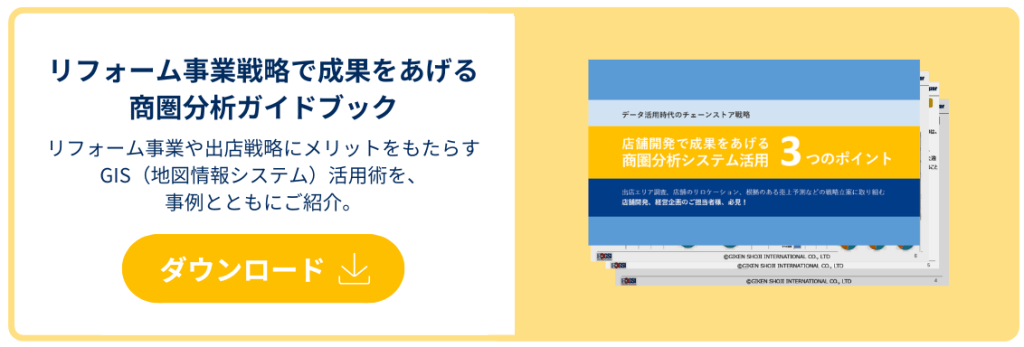
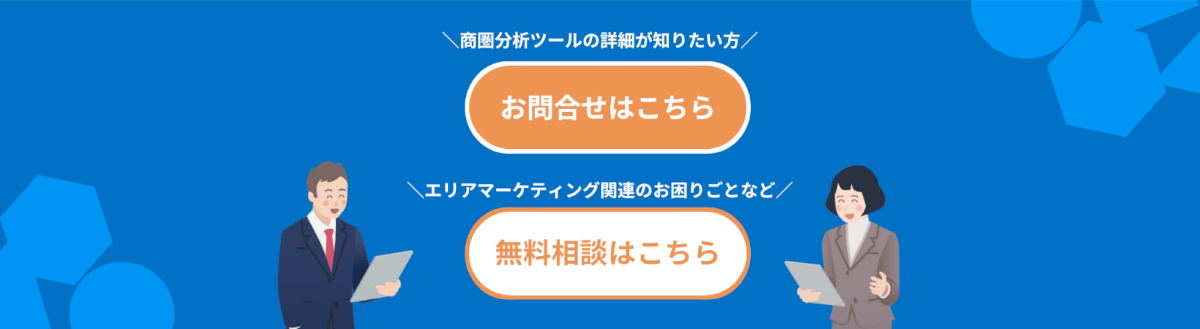
監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |
|
| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |
 |
電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)
Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/







