
エリアマーケティングラボ
総務省「家計調査」から見る消費支出データ活用術
エリアマーケティングを成功に導く分析と実践例
2025年8月19日号(Vol.168)
はじめに
日々の買い物、外食、家賃の支払い。これら無数の消費行動は、個人の生活を支えるだけでなく、集合体として日本経済の動向を映し出す巨大なデータとなります。この「消費支出」の動向を正確に把握することは、企業のマーケティング戦略や出店計画、商品開発において、成功の確率を飛躍的に高める指針となり得ます。
しかし、信頼できるデータの所在や具体的な活用方法について課題を抱える担当者は少なくありません。
本コラムでは、日本の消費支出を捉える上で最も信頼性の高い公的統計である、総務省統計局の「家計調査」を徹底的に解説します。調査の定義や仕組みといった基礎知識から、地域別・年代別の具体的な支出傾向、そして商圏分析用GIS(地理情報システム)を用いた実践的なマーケティング戦略への応用例まで、エリアマーケティングの専門家が詳述します。
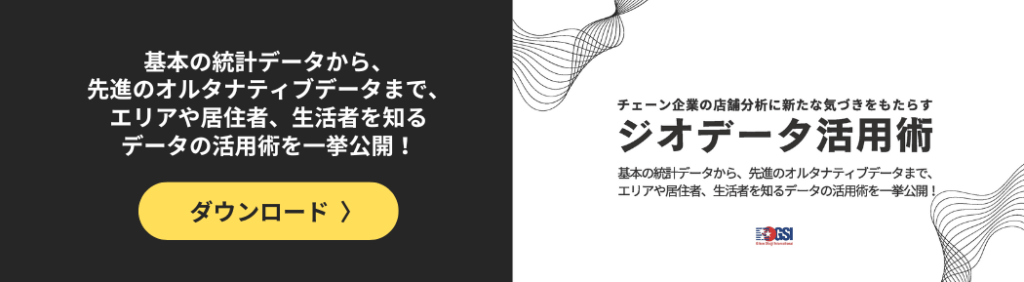
消費支出とは?その定義と家計調査の全体像
マーケティング分析の第一歩は、用語の正確な理解から始まります。
消費支出と非消費支出の違い
家計調査における支出は、「消費支出」と「非消費支出」に分類されます。
• 消費支出:
食料品や衣料品の購入、家賃、光熱費など、生活に必要な商品やサービスへの支出を指します。これは、市場規模や顧客の購買力を直接的に示す重要な指標です。
• 非消費支出:
所得税や社会保険料など、世帯の自由な意思で使い道が決められない義務的な支払いです。ビジネスにおいては、自社の商品やサービスが対象とする市場の潜在能力を測る上で、「消費支出」が不可欠なデータとなります。
家計調査:日本経済を支える基幹統計
消費支出データを継続的かつ網羅的に提供しているのが、総務省統計局が実施する「家計調査」です。これは、統計法に基づく国の最も重要な「基幹統計」の一つであり、国民生活の実態を全国規模で正確に把握することを目的としています。
家計調査は、その前身である「消費者価格調査」を含めると70年以上の歴史を持ち、その信頼性と価値は歴史によって証明されています。

家計調査の仕組み:信頼性の高いデータが生まれる背景
家計調査のデータが高い信頼性を持つ背景には、厳格な調査設計と実施プロセスがあります。
調査対象と精緻なサンプリング手法
家計調査は、日本全国の世帯が母集団ですが、その中から統計理論に基づき、公平に代表となる世帯を選び出す標本調査です。調査対象となるのは全国約9,000世帯で、この選定には層化3段抽出法という精緻な手法が用いられています。
1. 第1段抽出:
全国の市町村を、都道府県庁所在地や政令指定都市、人口規模、産業的特色などに基づき168の層(グループ)に分け、各層から1市町村を無作為に抽出します。これにより、大都市から地方の町村まで、日本全国の縮図となるような地域が選ばれます。
2. 第2段抽出:
選ばれた市町村内で、国勢調査の調査区を基にした単位区を無作為に選びます。
3. 第3段抽出:
選ばれた単位区内の全世帯の名簿を作成し、そこから乱数表などを用いて調査対象となる世帯を無作為に抽出します。
調査の精度を保つため、特定の世帯が続けて対象にならないよう配慮されており、二人以上の世帯は6か月、単身世帯は3か月で調査を終え、順次新しい世帯と交替します。また、収支の把握が困難な学生の単身世帯や外国人世帯などは調査対象から除外されています 。この厳格な設計が、データを「日本全体の平均的な姿」を反映したものにしています。
データ収集と公表スケジュール
調査対象世帯は、日々の収入と支出を「家計簿」に詳細に記入します。近年では、オンラインでの回答も導入されています。
収集されたデータは、総務省統計局に集められ、審査・集計を経て公表されます。
• 二人以上の世帯: 毎月速報公表
• 単身世帯及び総世帯: 四半期ごと
• 家計調査年報: 毎年刊行
この定期的な公表により、企業は常に最新の消費動向を把握できます。

家計調査でわかる消費支出 項目一覧
家計調査の最大の特長の一つは、その圧倒的な品目数の多さです。消費支出は大きく以下の10大費目に分類されます。
1. 食料
2. 住居
3. 光熱・水道
4. 家具・家事用品
5. 被服及び履物
6. 保健医療
7. 交通・通信
8. 教育
9. 教養娯楽
10.その他の消費支出(諸雑費、こづかい、交際費など)
この詳細なデータにより、「同じ食料費でも、生鮮食品と冷凍調理食品のどちらへの支出が多いか」といった具体的な消費スタイルの違いを分析できます。
日本の消費支出トレンド:地域・年代別の特徴を分析
家計調査のデータを時系列や地域、年代といった切り口で分析することで、日本の消費社会のダイナミックな変化と多様な姿が浮かび上がってきます。

長期的な消費支出の推移:名目と実質の違い
消費支出の動向を分析する際には、「名目」と「実質」という二つの指標を区別することが重要です。
• 名目消費支出: 実際に支払った金額そのもの。(物価の変動含む)
• 実質消費支出: 名目消費支出から物価変動の影響を取り除いたもの。消費者の実質的な購買力や生活水準の変化を示します。
真の消費動向を捉えるには、物価変動を排除した実質消費支出の推移を見ることが不可欠です。
都道府県別・年代別の消費支出ランキング
日本の消費支出は、地域や世帯主の年齢によって顕著な差が見られます。
地域による消費支出の差
都道府県別に1世帯当たりの消費支出を見ると、大きな地域差が存在します。総務省統計局のデータによると、支出額が多いのは関東地方などの都市部で、少ないのは沖縄県や九州、東北地方の各県という傾向が見られます。都道府県庁所在市別・1世帯当たり年間消費支出額ランキング(2022年・抜粋)
|
順位 |
市名 |
年間消費支出額(円) |
|
|
1 |
さいたま市 |
3,897,519 |
|
|
2 |
東京都区部 |
3,859,597 |
|
|
3 |
大津市 |
3,833,475 |
|
|
4 |
名古屋市 |
3,832,126 |
|
|
5 |
富山市 |
3,801,610 |
|
|
... |
... |
... |
|
|
48 |
宮崎市 |
3,061,061 |
|
|
49 |
長崎市 |
3,059,579 |
|
|
50 |
鹿児島市 |
3,026,381 |
|
|
51 |
那覇市 |
2,878,416 |
|
|
52 |
青森市 |
2,869,322 |
|
出典:総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯) 2022年」のデータを基に作成
地域差の要因:
この表が示すのは、単なる順位だけではありません。1位のさいたま市と52位の青森市では、年間で100万円以上の差があり、市場のポテンシャルが地域によって大きく異なるという厳然たる事実です。この差が生まれる要因を費目別に見ると、「食料」のような生活必需品の地域差は比較的小さい一方、「教育」や「住居」、「教養娯楽」といった費目で大きな差が見られることが分かっています。これは、教育熱心な地域や住宅価格が高い都市部で、これらの支出が嵩むことを示唆しています。
年齢による消費支出の差
消費支出はライフステージと密接に関連しており、世帯主の年齢と共に上昇し、50歳代でピークを迎えた後に減少するパターンが見られます。• 費目の特徴:
20代は「住居」費、40代は「教育」費、70歳以上は「食料」費の割合が高くなる傾向があります。
これらの分析は、市場が地理的・人口動態的な軸が交差する複雑な構造であることを示しています。そして、この複雑な分析を可能にするのが、次で解説するGISの活用です。
消費支出データのマーケティング活用例
エリア分析から販促計画まで
家計調査から得られる消費支出データは、そのままだと膨大な統計表に過ぎません。しかし、これをエリアマーケティングの視点で活用することで、企業の様々な意思決定をデータドリブンで裏付ける強力な武器となります。

▼小地域単位の消費支出データ
https://www.giken.co.jp/datalineup/statistics/expenditure/
活用例1:新規出店戦略・有望立地の選定
新規出店は企業にとって大きな投資であり、その成否は事前の商圏分析の精度に大きく左右されます。消費支出データは、出店候補地の市場ポテンシャルを客観的に測定するための根幹となります。
例えば、飲食店の出店を検討している場合、GIS(地理情報システム)上で候補地周辺の商圏を設定し、そのエリアの「外食」に対する年間消費支出額を算出します。さらに、そのエリア内の競合店の数や規模を考慮することで、市場の飽和度や、まだ満たされていない需要(=ビジネスチャンス)が存在するかを判断できます。あるエリアの「外食」への支出意欲は高いにもかかわらず、飲食店の供給が少ない場合、そこは有望な出店候補地である可能性が高いと結論付けられます。
活用例2:販促計画の最適化と広告出稿
限られた広告予算を、最も効果の高いエリアとターゲットに集中させることは、販促活動のROI(投資対効果)を最大化する上で不可欠です。消費支出データは、販促の重点エリアを特定するのに役立ちます。
例えば、スーパーマーケットが高級輸入食材の販促キャンペーンを行うとします。GISを用いて、商圏内のエリア(町丁目単位など)ごとの「調理食品」や「菓子類」「酒類」といった関連品目の消費支出額を地図上に色分けして可視化します。これにより、支出額が高い、つまり購買意欲が高い潜在顧客が多く住むエリアがひと目でわかります。そのエリアにターゲットを絞ってチラシをポスティングしたり、ジオターゲティング広告を配信したりすることで、無駄な広告費を削減し、高い反応率が期待できるでしょう。
活用例3:MD(マーチャンダイジング)計画と商品構成の最適化
店舗の品揃えは、その地域の顧客ニーズに合致している必要があります。消費支出データは、地域ごとの消費パターンを詳細に分析し、店舗ごとの最適な商品構成を考える上での重要な指針となります。
例えば、同じドラッグストアチェーンでも、単身者が多く「弁当」や「冷凍調理食品」への支出が多いオフィス街の店舗では、中食・惣菜コーナーを充実させるべきです。一方、ファミリー層が多く「紙おむつ」や「育児用品」への支出が多い郊外の店舗では、ベビー用品の品揃えを手厚くするといった判断が可能になります。GIS上で品目カテゴリーごとの消費金額をシミュレーションし、棚割構成や売場面積の最適化に繋げることもできます。

活用例4:顧客分析とペルソナの解像度向上
自社の顧客データが十分にない場合でも、消費支出データを用いることで、店舗の商圏内に住む人々の大まかなライフスタイルや所得水準を類推することが可能です。
例えば、ある店舗の商圏で「教養娯楽サービス(月謝など)」や「教育」への支出が高い場合、そのエリアには教育熱心なファミリー層が多く住んでいると推測できます。また、「自動車等関係費」や「交通・通信」への支出が高いエリアは、車社会であるか、あるいは情報通信への感度が高い層が多い可能性があります。こうした分析は、ターゲット顧客のペルソナをより具体的に描き出すための基礎情報となります。
これらの活用例に共通するのは、消費支出データが「どこに、どのような需要が、どれだけあるか」を客観的な数値で示すことで、企業の資源(投資、販促費、在庫、棚スペース)配分を最適化する役割を果たすという点です。これにより、マーケティング活動は「勘と経験」に頼ったものから、データに基づいた「科学的な投資」へと進化するのです。
「なぜ買うのか?」を解明する
消費支出と消費者ライフスタイルデータの連携
消費支出データは、「何が」「どこで」「いくら」消費されているかという、市場の「行動の結果」を克明に示してくれます。しかし、現代の多様化した市場で競争優位を築くには、「なぜ消費者はそれを買うのか?」という、行動の裏にある「動機」や「価値観」まで踏み込む必要があります。
「WHAT」から「WHY」へ:分析の限界と新たな視点
例えば、A地区とB地区の「被服及び履物」への年間消費支出額が全く同じだったとします。しかし、その内実を見てみると、A地区の住民は「流行のファッションやブランド品」を好み、B地区の住民は「長く使える丈夫なもの、コストパフォーマンス」を重視しているかもしれません。
この二つの市場に対して、同じ商品、同じメッセージでアプローチしても、成功はおぼつかないでしょう。消費支出データ(WHAT)だけでは、こうした消費者の内面的な違い、すなわちサイコグラフィック(心理的属性)を捉えることは困難です。
サイコグラフィックを可視化する「消費者ライフスタイルデータ」
この「WHY」の領域を解明するのが、価値観、趣味嗜好、ライフスタイルといった消費者の心理的な側面を捉えた消費者ライフスタイルデータです。
当社、技研商事インターナショナルでは、大規模なリサーチから得られた生活者の意識や行動に関するデータを、小地域単位で分析可能にした「消費者ライフスタイルデータ」を提供しています。
このデータは、「環境問題への関心度」「健康志向の度合い」「情報収集で重視するメディア」「休日の過ごし方」など、数百項目にわたる詳細な意識・行動データを含んでいます。

2つのデータの連携が生み出す、高解像度な顧客ペルソナ
消費支出データ(行動の結果)と消費者ライフスタイルデータ(行動の動機)を連携させることで、ターゲット顧客のペルソナ(人物像)は劇的に具体的かつ鮮明になります。
【分析例:カフェの出店戦略】
• 消費支出データ(WHAT):
GIS分析により、エリアXでは「コーヒー豆」や「喫茶代」、「書籍」への支出が全国平均より著しく高いことが判明。
• 消費者ライフスタイルデータ(WHY):
同じエリアXの住民は、「一人の時間を大切にしたい」「知的な刺激を好む」「落ち着いた空間で過ごしたい」といった意識スコアが高いことが判明。
【導き出されるインサイトと戦略】
• ペルソナ:
このエリアのターゲットは、単にコーヒーが好きなだけでなく、「静かな環境で読書をしながら質の高い時間を過ごしたいと考える "思索的な個人"」であると定義できます。
• 戦略:
画一的なチェーンカフェではなく、蔵書が豊富で座席間隔が広く、静かなBGMが流れる「ブックカフェ」という業態が最適であると判断。プロモーションも、SNSでの賑やかな告知より、地域の書店と提携したり、文芸雑誌に広告を出したりする方が効果的であると推測できます。
このように、2種類のデータを掛け合わせることで、企業は市場のトレンドに後から対応するのではなく、消費者の潜在的なニーズを先読みし、市場を創造するような戦略を立てることが可能になります。これは、単なる市場追随者から市場の主導者へと脱皮するための、極めて強力なアプローチです。
エリアマーケティングを革新するGISと最新年間消費支出データ
これまで見てきたように、消費支出データやライフスタイルデータは、マーケティング戦略に不可欠な情報資産です。しかし、これらのデータは、市区町村別、品目別、年齢階級別など、膨大な数の統計表として提供されるため、そのままではビジネスの現場で直感的に活用することは困難です。
この「データの壁」を乗り越え、膨大な数値を誰もが理解できる「戦略地図」へと変換する技術が、GIS(地理情報システム)です。
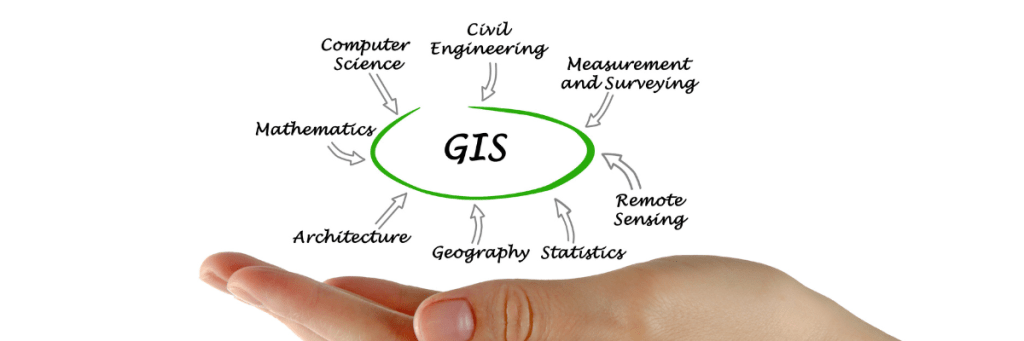
GISが実現する「データの可視化」と「高度な分析」
GISは、人口、世帯、年収、そして消費支出といった様々な統計データを地図上に重ね合わせ、色分けやグラフで表現することで、エリアの特性を視覚的に把握することを可能にします。
当社が提供する商圏分析用GIS「MarketAnalyzer® 5」は、全国2,000社以上の導入実績を誇る、エリアマーケティングのデファクトスタンダードです。MarketAnalyzer® 5は、単に地図上にデータを表示するだけでなく、ビジネスの意思決定を直接支援する高度な分析機能を多数搭載しています。
• ポテンシャルエリアの検索:
「特定の品目への消費支出が高く、かつ競合店が少ない」といった複数条件でエリアを抽出し、出店の有望エリアを自動でリストアップします。
• 顧客分布とシェアの可視化:
自社の顧客データを地図上にプロットし、どのエリアから顧客が来ているか、各エリアの人口に対して自社の顧客が占める割合(シェア)はどのくらいかを分析できます。
• 精緻な売上予測:
既存店の売上と商圏データ(人口、世帯年収、消費支出など)の関係性を統計的に分析(重回帰分析)し、新規出店候補地の売上を予測するモデルを構築できます。また、競合店の存在を考慮した吸引力を計算するハフモデル分析なども可能です。
技研商事インターナショナルが提供する「使える」消費支出データ
当社では、総務省が公表する家計調査のデータをそのまま提供するだけではありません。これらの公的統計を、ビジネスで最も活用しやすい町丁・字等別やメッシュといった小地域単位に推計・加工した、独自のデータベースとして提供しています。これにより、市区町村単位では見えなかった、よりミクロで詳細な商圏の特性を捉えることが可能になります。
当社が提供する豊富なデータラインナップには、本コラムで解説した消費支出データはもちろん、国勢調査に基づく人口・世帯データ、推計年収データ、将来人口データ、そして前述の消費者ライフスタイルデータなどが含まれており、これらをGIS上で自在に組み合わせることで、多角的で深いエリア分析が実現します。
GISは単なる地図作成ツールではありません。それは、データに基づき「もしここに出店したらどうなるか?」「このエリアに広告を打つべきか?」といった戦略的な"What-if"シナリオをシミュレーションし、意思決定の質を飛躍的に高めるための「戦略的思考環境」なのです。
【無料トライアル】最新の年間消費支出データを搭載したGISを体験

GIS(地理情報システム)と最新の年間消費支出データを組み合わせることで、より高度なエリアマーケティングが可能になります。無料トライアルでは、これらの機能を実際に体験(トライアル)いただけます。
このトライアルでは、製品版とほぼ同等の機能を、実際のデータを用いてご自身のPCで心ゆくまでお試しいただけます。
• AIによる商圏レポート:
地図をクリックするだけで、AIが商圏の特性を文章で要約。分析の専門知識がなくても、誰でも簡単にエリアのポテンシャルを把握できます。
• 高精度な分析機能:
本文で紹介した売上予測や顧客分析、重点エリア抽出など、高度な分析機能を実際に操作し、その効果を体感できます。
• 万全のサポート体制:
2,000社以上の導入実績に裏打ちされた専門スタッフが、トライアル期間中も操作方法から分析のコツまで、手厚くサポートします。ツールを渡して終わり、ということは決してありません。
データに基づいた客観的な意思決定は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。この機会に、データドリブンなエリアマーケティングの世界を、ぜひご自身でご体験ください。
▼最新の消費支出データを搭載した商圏分析用GISの無償提供はこちらから
https://www.giken.co.jp/mka-lp202304
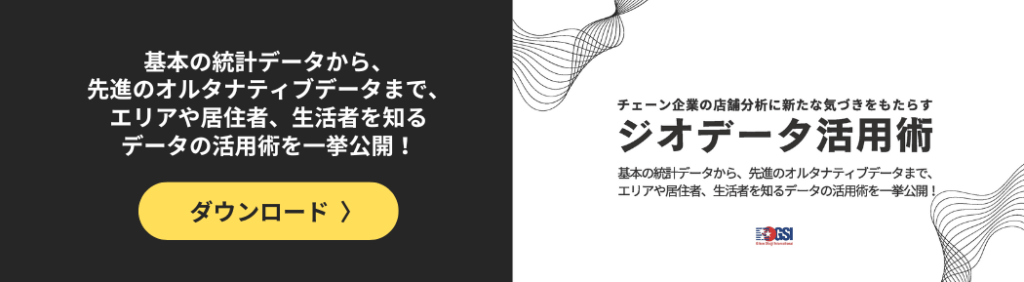
監修者プロフィール市川 史祥技研商事インターナショナル株式会社 執行役員 マーケティング部 部長 シニアコンサルタント |
|
| 医療経営士/介護福祉経営士 流通経済大学客員講師/共栄大学客員講師 一般社団法人LBMA Japan 理事 Google AI Essentials Google Prompt Essentials 1972年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。不動産業、出版社を経て2002年より技研商事インターナショナルに所属。 小売・飲食・メーカー・サービス業などのクライアントへGIS(地図情報システム)の運用支援・エリアマーケティング支援を行っている。わかりやすいセミナーが定評。年間講演実績90回以上。 |
 |
電話によるお問い合わせ先:03-5362-3955(受付時間/9:30~18:00 ※土日祝祭日を除く)
Webによるお問い合わせ先:https://www.giken.co.jp/contact/






